多文化クロストーク
「子育て」について ー第3回 幼稚園・保育園・学校入学ー ~中国、ロシア、アメリカ出身者が語る~
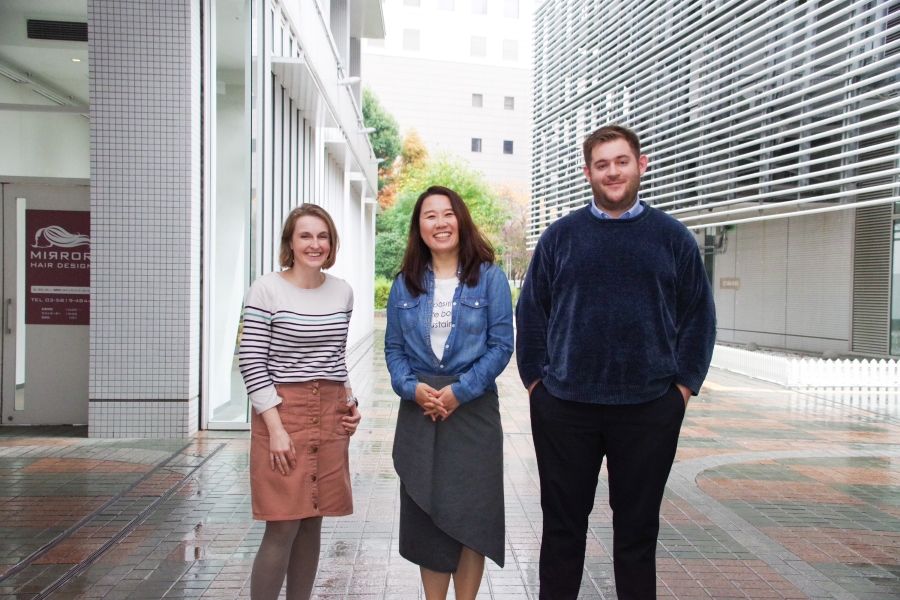
メンバープロフィールをチェック
第1回はコチラから第3回 幼稚園・保育園・学校入学について
子育てについて3回シリーズでお届けしています。最終回は子どもたちが育っていく中で、幼稚園や学校について話していただきました。母国と違うことがいろいろあるそうです。
ママ友・パパ友や子育ての仲間はいますか

子どもと公園へ行くのは週末です。子どもを遊ばせるパパたちは結構いますね。公園で他のパパたちに会うことはありますが、友だちではありません。
最近、公園にパパが本当に増えています。
わたしはママ友をすごく必要としていました。ひとりで心が痛かったから。公園や児童館のサークルとかでも話しかけたりして、頑張っていました。わたしを見ると日本語が分からないだろうと思われるので、日本語ができるアピールをしたかったんです。
子どもが幼稚園に入ったら、自然にママ友ができました。。
二人の息子が通っていたスポーツに特化した幼稚園では、みんなでLINEのグループを作ってそこで会話をしていました。友達は時間をかけてやり取りをしないと作れないと思いますが、やり取りの時間がありません。LINEで会話はするけれど、そうした意味ではママ友はいないかもしれません。子どもが同い年のママ友じゃなくても、会社の先輩で子育てしている人もいるので、相談したりアドバイスを求めることはよくあります。
うちの奥さんは日本人ですから同級生や先輩もいるので、子育ての話をする仲間はいると思います。
「ママ友」の意味は、子どもの話をする友達ですか。それはあまり必要としていないですね。楽しく会話できるくらいでいいです。求めているのは、話をしたり、一緒にどこかへ行ったりできる友達です。わたしは共通の趣味がある人がいいです。
そうですね、趣味が一緒の友達がいいですね。
日本に住む同じ国出身の子育て仲間と情報交換しますか
わたしは日本在住の中国人ママのコミュニティを作りました。WeChatで1,300人ほど参加しています。通っている進学塾によって、4つのグループに分かれています。働くママのコミュニティもあって、そこではけっこう盛んにコミュニケーションしています。
わたしはFacebookですね。「日本のママ」という、日本在住の子育てしているロシア人たちのグループです。情報としては、イベントやロシア関係のことです。男性は入らないですね。また、働いているママのFacebookもあります。仕事や子育ての悩みの相談ですね。
アメリカ人の日本に住んでいるグループもあると思うんですけど、わたしは参加していません。
たぶん、男性だからだと思います。アメリカ出身者でも女性のグループはあると思います。男性はグループに関心を持たないみたいですね、中国人も一緒です。
英語を話せる人が多いので、アメリカ出身だけじゃなくても、いろいろなグループがありそうです。人種よりも言葉が通じたほうが、仲間ができやすいと思います。
幼稚園や保育園は日本と同じですか

(中国では)わたしが子どものころは、3歳前に入るところと、3歳以降に入る幼稚園がありました。親が働いているかどうかは関係がなく、子どもを預けたいかどうかで決められました。今はみんな祖父母やベビーシッターにお願いしながら3歳まで育てて、3歳から幼稚園に入ります。
アメリカの保育園のようなものに、生まれてすぐに預けられるデイケアがあります。全部自費ですから入るための制限はあまりないです。デイケアはかなり高いので、仕事を辞めて子育てをする女性も多いです。小学校に入る前は、みんな幼稚園へ入ります。都会と田舎、地域の文化によっても、全然違います。
ロシアも保育園みたいな施設は足りないです。子どもを産んでから申請をします。日本と似ていますが、働いているか働いていないかは関係ありません。3歳からはだいたいみんな入りますけど、日本のように何歳になったら申し込みをして、何月で締め切る、というようなことはあまりありません。自分のタイミングで申請することができます。
みなさんの子どもは幼稚園ですか、それとも保育園に行きましたか
長男は、最初は保育園でしたけど、5歳のときにスポーツに特化した幼稚園に通い始めました。次男は初めから、長男と同じところに入れました。
うちの子どもは二人とも、同じ保育園です。市役所に12月くらいに行って申請し、4月から入ることができました。
わたしは毎日子供と離れたくなかったから、週3回通えるところを探しました。インターナショナルプリスクールを見つけて、そこに通っています。
入園してから苦労したことはありますか
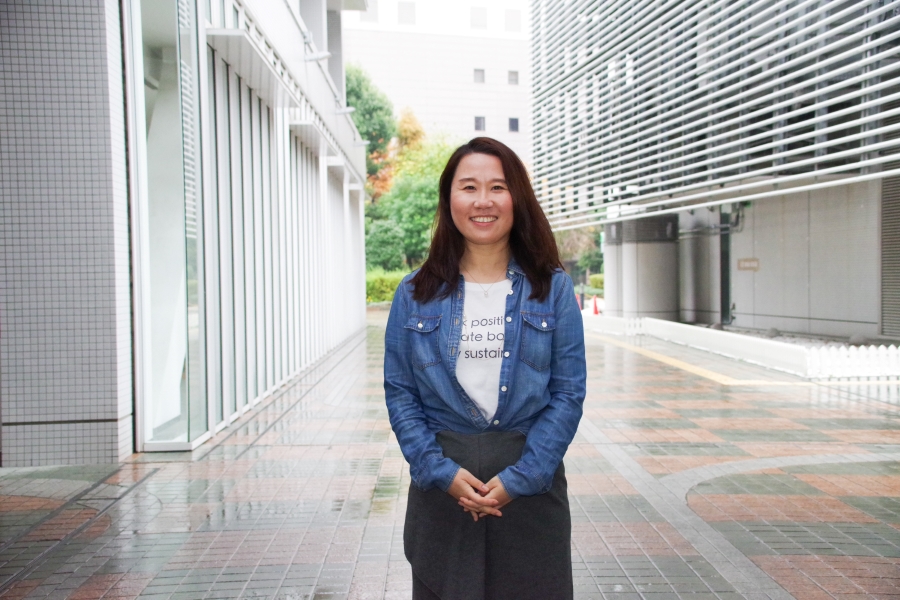
子どもたちの通っていた幼稚園は、専業主婦の方がほとんどだったんです。働いているママは、1クラスに2~3名ぐらいです。午後にお茶をしながら子どもの話をしたり、イベントで使うものをみんなで手作りしていたんですが、フルタイムで仕事をしていたので、その輪に入れませんでした。
苦労したことはあまりないんですが、いろいろな決まりにイライラしました。例えば上履きは白じゃなきゃいけないとか、幼稚園のイベントは平日だけとか。イベントは月に3~4回あるんですが、働いているので参加できないんです。何度も交渉して、少し変わりました。
とても残念だったことがあります。保育園のプール遊びで毎日提出する紙があって、印鑑を押さなければならないんです。わたしが連れて行ったときに印鑑じゃなくてサインをしたんですが、「印鑑ではないから」という理由で「入ってはダメ」と言われてびっくりしました。わたしが毎日保育園へ連れて行くし、保育園参観もしているのに…。子どもはとても楽しみにしていましたが、結局入ることができなくて帰らされたんです。
それはひどいですね。子どもに対してひどいと思います。サインの方がよほど本人とわかるのに。
今、私の子どもは5歳半なんですが、今の時点でこの先の学校について悩んでいます。インターナショナルスクールか公立学校か…インターナショナルスクールは高校がありませんし、公立学校の場合は子どもの日本語が心配です…。
学校のこと、塾のこと

みなさんの国の学校制度について教えてください
中国は小学校5年、中校学4年、高校3年で、9月始まりです。
ロシアも9月始まりです。小学校4年、中学校5年、高校2年ですが、建物も一緒でクラスも最後まで一緒です。小学校に入ってクラスが決まったら、クラスは変わりません。いじめがあった場合や成績によってクラスを替えることはあります。担任の先生が変わることはありますが、仲間はずっと一緒です。
アメリカの学校制度は州によっても市によっても変わります。わたしの地元ですと小学校は4年、ミドルスクール3年、ジュニアハイスクール3年、シニアハイスクール2年です。学校は8月始まりです。
ロシアは6歳半で小学校に入ることはできるんですが、入る年は基本的には親が決めます。6歳になったばかりでも8歳でもいいんです。例えば、この子は字が読めないから1年スキップしようとかを、入学前に先生に相談することができます。
それはいいと思いますね。
日本の子どもたちは塾に通っている子が多いですが、学校があるのに何で塾があるんですか。よくわかりません。ロシアには塾はあまりありません。
そうですね。アメリカも塾はほとんどないです。
中国には塾がありますよ。
子どもの成績が心配な人は、個人指導をしてくれる先生の所に通って、いい大学を目指すということがロシアにもあるようです。
中国の人は教育熱心で、良い学校があればお金がなくても子どもを優先させますので、受験率は日本に比べて、断然高いと思いますよ。みなさん塾に通わせて、目標とする学校を目指します。学校だけでは難しいという話を聞いたことがあります。わたしも子どもが小さいときは、なんで学校と塾と2つ通わせないといけないの、とは思いました。
塾にも試験とかあるようですね。
子どもはいつ遊ぶんですかね。
「子育てについて」は、それぞれに経験したことがたくさんあり話題が広がりました。子どもたちを通して、日本の仕組みを知ることも多いようです。3回シリーズは今回で一度終わり、5月号は特別編として、TIPS(東京都多文化共生ポータルサイト)の「ニュースレター」について話していただきます。
