多文化クロストーク
ルーツの国・日本に来た人たちー第1回 私の生まれた国、育った国ー
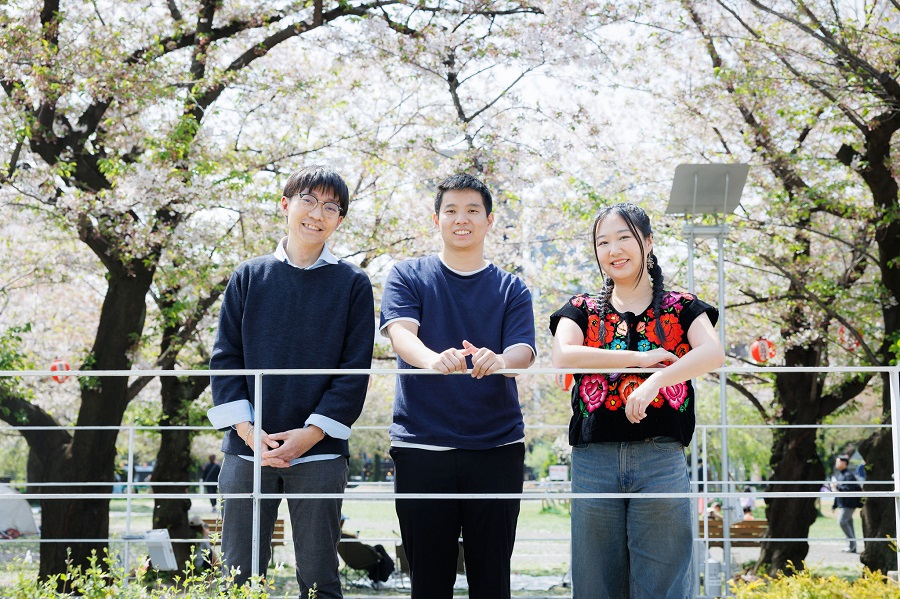
3人のプロフィール
しんや(韓国出身)
- 在住年数
- 7年
- 母語
- 日本語と英語
- 好きな日本語
- 一期一会
- 東京で好きな場所
- 東側全域、隅田川沿い
- 好きな食べ物
- じゃがいもを使った料理
- 趣味
- 読書と映画鑑賞
- 1週間の休みがあったらどこに行きたいか
- ドイツ
ゆうき(アルゼンチン出身)
- 在住年数
- 19年(一度帰国し、日本に戻ってきてからは8年)
- 母語
- スペイン語と日本語
- 好きな日本語
- 初心忘るべからず
- 東京で好きな場所
- 隅田川
- 好きな食べ物
- 寿司
- 趣味
- 旅行
- 1週間の休みがあったらどこに行きたいか
- 与論島
さや(メキシコ出身)
- 在住年数
- 13年
- 母語
- スペイン語と日本語
- 好きな日本語
- 人(漢字の由来を知ってから)
- 東京で好きな場所
- 表参道
- 好きな食べ物
- ラーメン
- 趣味
- 旅行
- 1週間の休みがあったらどこに行きたいか
- パラオ諸島
第1回 私の生まれた国、育った国
「ルーツの国・日本に来た人たち」の座談会を 3回シリーズでお届けします。
海外で暮らす人の中にも、日本にルーツを持つ人たちがたくさんいます。今回は海外で生まれ育ちながら、自分の意思でルーツのある日本に来ることを選んだ三人に、決断の理由や育った国のこと、自身のアイデンティティに関する考えについて話を聞きます。
あなたが日本のほかにルーツを持つ国、育った環境について教えてください。

アルゼンチンにルーツがあります。小学 5年生まで日本にいて、その後家族でアルゼンチンに移り、何度か行き来してきました。アルゼンチンではブエノスアイレスの郊外のほうに住んでいました。
私はメキシコのクエルナバカという街で育ちました。メキシコシティから1時間くらいの距離で、昔はのどかでしたが、今はかなり都市化が進んでいますね。
僕は母が韓国出身、父が日本出身です。韓国で生まれて、2歳のときに香港に移りました。アメリカの大学に進学するまでは、家族で香港に住んでいました。
日本に来ようと思ったきっかけはなんですか?
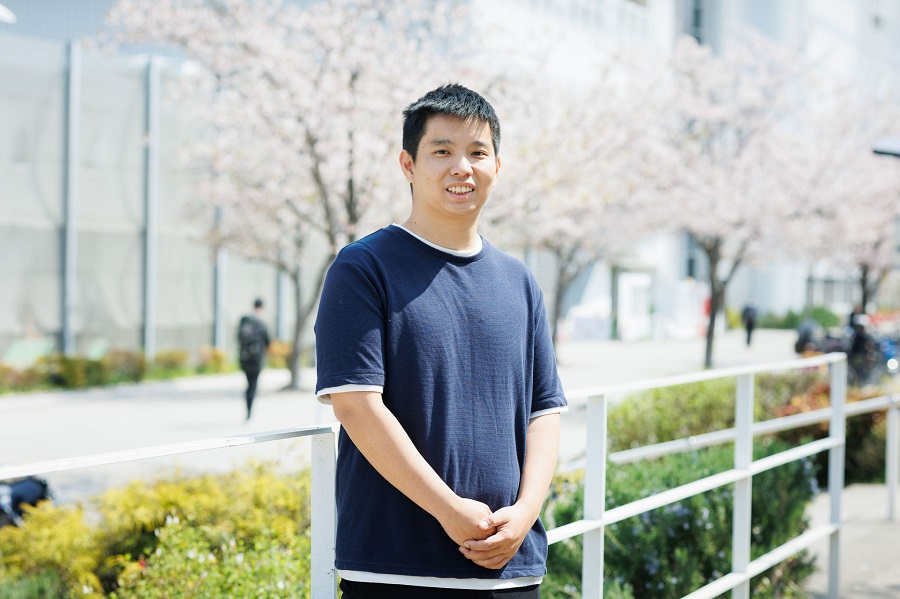
実は、日本に来ることは全然想定していなかったんです。メキシコの高校卒業を前に、これから何を勉強しようか考えていたときに、日墨協会(注:日本とメキシコの交流を目的とする団体)の雑誌に、日本財団などが日本での進学に奨学金を出していることを知りました。日本には祖母が住んでいるので遊びに来たことはありましたが、自分が暮らす発想はありませんでした。でもその後運よく奨学金をもらえることになり、2012年に来日して服飾系の専門学校に進みました。
僕も高校卒業後に日本に来ましたが、「日本に行きたい!」という強い思いはなかったです。高校時代に日本に留学する機会があり、そのまま大学に通うことになった感じです。アルゼンチン出身者が多く、自分の父も通った大学があったので、そこに決めました。
日本で長く生活するのは小学 5年生以来だったので、日本に関するすべての知識がそのときで止まっていました。日本語もかなり忘れていましたね。
僕はお二人と違い、仕事をきっかけに来日しました。
アメリカの大学院で教育政策学を学んでいるとき、さまざまな国の教育を比較して、日本の生徒は学力が高いとされている反面、人の幸せには紐づいていない感覚を持っていました。
自分は小学校 6年間と中学校の 1年生まで香港の日本人学校に通っており、とても楽しい学校生活を過ごしました。日本の文化や教育制度は理解していたので、ではどこが問題なんだろうと考え、日本の教育に携わりたいと思ったことが日本に来たきっかけです。
日本の教育についてはどう感じましたか?
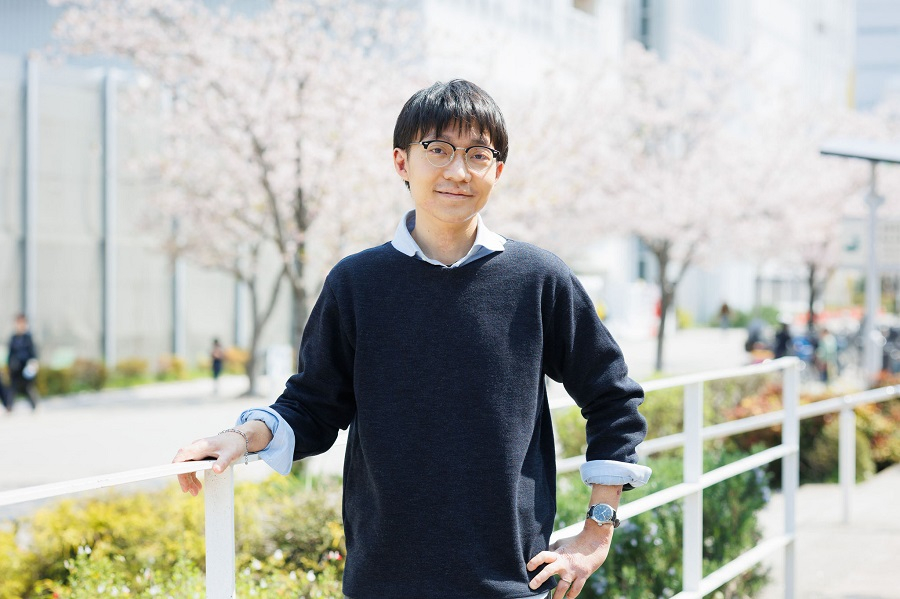
とりあえず、大学は楽しかったですし、周りもみんな楽しそうでした。だけど就職すると印象がまったく異なり、それが不思議でした。みんな大変そうというか、病んでいそうな感じで。
私は専門学校でしたが、日本って「いい高校」「いい大学」など進路に関してのプレッシャーがすごく強いんだな、というのは来て感じました。メキシコにいるときは、夏休み前は「どこ遊びに行こうか」という話ばかりでしたが、日本は宿題などの話題が多いです。
南米の教育環境は、日本と真逆なんですよね。アルゼンチンは高校までが楽なんですけど、大学を卒業するのは大変で、4年で卒業する人が珍しいです。大学に何年か行って、勉強しながらゆっくりやりたいことを探すという人が多かったです。
自分の専門分野でもあるのですが、教育は、まずそれぞれの国によって「こうあってほしい」という人物像があり、その理想を目指してカリキュラムが組まれますよね。日本は、世間と呼ばれる社会性と自分との関係性が強い文化だと感じます。だから学生自身のしたいことよりも、社会性に対する個人のあり方というように、社会性と個人を比較する機会が多く、自分なりのしたいことを突き詰めるのが難しい側面があるのかなと思います。
何歳くらいから、自分のルーツやアイデンティティについて考えるようになりましたか。

子どものころ、日本にいるときは日本語のみで暮らしていました。小学5年生でアルゼンチンに移り、スペイン語圏で暮らす中で、徐々に自分の考え方が変わっていくのを感じました。日本の考え方から、日本とアルゼンチン両方の考え方になっていった感じでしょうか。
日本にいたときは、休みの日も家族といるより友達と遊んでいました。でも、アルゼンチンは週末必ず家族と過ごします。日本ではほとんど親戚に会ったことがありませんでしたが、アルゼンチンでは会ったことない親戚がどんどん出てくる。最初の歓迎会なんて30人くらい親戚が集まって、いとこのいとことか、全然知らない人ばっかりじゃんと思いました(笑)。
ルーツについては、大学で日本に戻ってきてから気になり始めました。日本で初めて自分が外国人扱いされたからですかね。
それ、わかります。
私もメキシコだと普通に暮らしていたし、日本語はむしろできるほうで、スピーチコンテストでも褒められていました。でも日本に来ると、固有名詞など読めないことがあり、結構困りました。駅員さんに駅の読み方を聞いたりするたび、「大人なのにこれも読めないの?」と不思議に思われているのを感じて、気まずかったです。
今はもう、外国人とバレなくなったので大丈夫です(笑)。
私の場合、自分のルーツについては日本に来る前から結構悩んでいました。私は幼稚園から高校まで、ヨーロッパ系の学校に通っていたんです。家だとアジア、外だとラテン、学校はヨーロッパ。3つの文化の中で、なんとなく疎外感を感じるようになりました。
ただ、高校のとき日系メキシコ人のサマーキャンプに参加して、そこからかなり性格が明るくなりました。自分と近いバックグラウンドの人たちに会えたことが大きかったんだと思います。
今はメキシコのルーツを持ちながら日本の文化を受け入れる、そういうダブルな自分でいいと思えるようになりました。
僕は香港、アメリカという自分のルーツとは別の国で、長い期間暮らしていました。香港だと「近隣国から来た外国人」、アメリカだと「アジア系外国人」など、「外国人である自分」がアイデンティティの中心でした。そのとき暮らす国の中で、自分がどういうとらえ方をされているのか、常に周りの認識を気にして生きてきた感じです。
家の中の共通言語は日本語でしたが、子どものころから母と韓国系の教会に通っていました。そこでは韓国語を学び、韓国系のコミュニティにも属していました。だから日本の国籍は持っていましたが、韓国や居住国を含め、「他の文化にもつながりがある」というのが自分の前提でした。だから、アイデンティティを形成する要素として国籍は一部に過ぎず、それ以外にもたくさんあると、昔から自然に思ってきました。
第1回は、異なる環境の中で育ち、それぞれの理由で日本に来た三人に、その背景を聞きました。
第2回では、「私と日本」をテーマに、三人が日本に来て抱いた日本観、文化や人についての印象を、さらに掘り下げます。
── 次号へ続く
