多文化クロストーク
外国につながる若者たちの座談会 ー第1回 言葉についてー

3人のプロフィール
さぶりな(ペルー出身)
- 在住年数
- 17年
- 母語
- スペイン語・ポルトガル語(今は日本語が1番得意です)
- 好きな日本語
- かわいい
- 東京で好きな場所
- 町田駅カリオン広場
- 好きな食べ物
- アイスクリーム
- 趣味
- 登山、アウトドア
- 好きな音楽
- ヒップホップ、ラテン音楽
ゆうこ(台湾出身)
- 在住年数
- 8年
- 母語
- 日本語と中国語(繁体字)
- 好きな日本語
- 能ある鷹は爪を隠す
- 東京で好きな場所
- 隅田川沿い
- 好きな食べ物
- ハンバーグ
- 趣味
- カラオケ
- 好きな音楽
- LOVE PHANTOM/B'z
プラギャン(ネパール出身)
- 在住年数
- 10年
- 母語
- ネパール語
- 好きな日本語
- 「少々お待ちください」(コンビニでバイトをした時に、最初に教わりました。便利な言葉なので、好きです)
- 東京で好きな場所
- 晴海
- 好きな食べ物
- カレー
- 趣味
- 研究
- 好きな音楽
- Killer-Tune/東京事変
第1回 言葉について
外国につながる若者たちの座談会を3回シリーズでお届けします。
今回は20代で友達になったという3人の若者に、リラックスした雰囲気の中で話していただきました。
現在は日本で生活する3人ですが、これまで国境を越え、さまざまな環境の中で成長してきました。どんなことを経験し、何を感じているでしょうか。
1回目は「言葉」についてです。異なる言語に揉まれながら育った子ども時代を振り返る3人のクロストークを見てみましょう。
日本語はどのように覚えましたか

父は日本人なので日本語で話しかけてきますが、子どものころのわたしは日本語が話せないから中国語で返事をしていました。読み聞かせのとき母は中国語で、父は日本語というバイリンガルでした。生まれたときから中国語と日本語が家庭内にありました。
話すのはどうやって覚えたんですか。
日本語を話すようになるのは、小学生として台北の日本人学校に入ってから。それまでは全部中国語でした。
僕は日本で生まれて、2歳ぐらいのときにネパールに戻りました。母に確認したら、日本に帰ってきたのが小学2年生で、最初の2~3か月は学校が終わると区役所の日本語教室に通っていたようです。
そこで日本語を話せるようになったんですね。
そうですね。そのときの記憶はありませんが、学校でみんなと日本語で話したことはよく覚えています。
早いですね。
多分、子どもは覚えるのが早いんだと思います。小学2年生から2年間日本にいて、またネパールへ戻りました。高校生のときに再び日本に帰ってきた時は、日本語は多少覚えていたので聞いたことは分かるんですけど、話せない。一度日本語を覚えて、忘れて、また覚えるという貴重な体験をしました。
わたしは10歳のときにペルーから日本に来て、日本語はゼロの状態でした。学校に通えないまま富山から、福岡、神奈川県へと移って、最初に学校に入ったのは小学4年生の3学期です。日本語を教えてくれる人もいないから覚えられなくて、日本語はほぼ独学です。最初に通った学校ではいじめられていたから、家では声が出せるけど学校では声が出せない「場面緘黙症」になりました。人前で喋るのが怖かったです。少しずつ話せるけど、教科書通りの敬語でしか話せなくて、変な人って思われていたと思います。
自分が他の人と同じぐらい話せるようになったのは、何年生のときですか。
高校生のときです。中学までは日本語を話している自分の声を聞かれるのが怖かった。ずっと日本語を話せない子と思われていたから、いきなり話したら、キモイとか言われるかもしれないので。高校生になると環境が変わるから、わたしのことを知っている人は少ないし、もういいやと思って話せるようになりました。
家族間では、何語で話していましたか
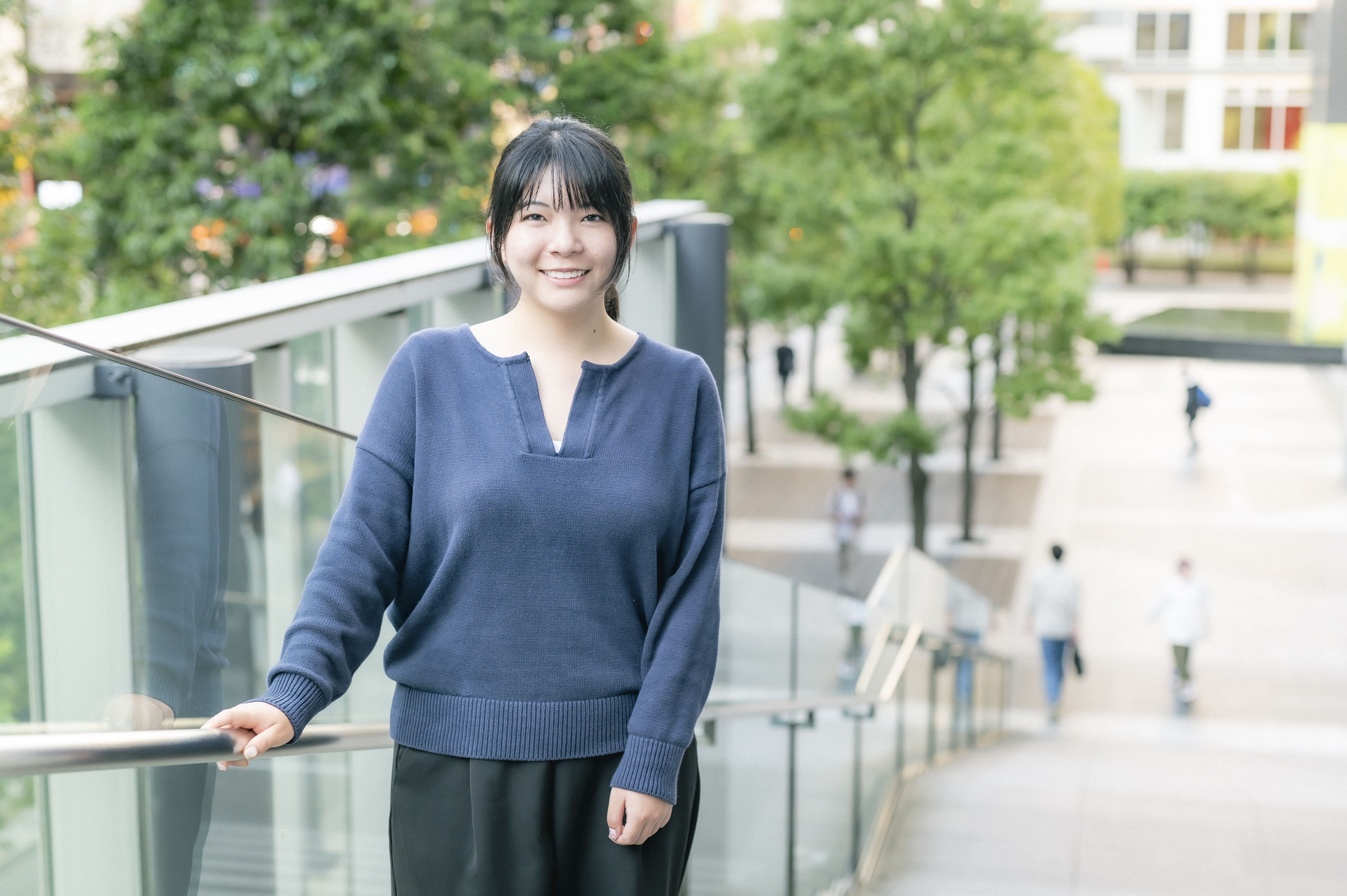
父と母の会話は中国語で、幼少期はほとんど中国語で親と会話をしていました。小学生から台北の日本人学校に入って日本語を覚え、父とフルに日本語を話せるようになったのは、小学3年生のときです。その前までは部分的に中国語でした。
今でも家の中で言葉が混ざったりしませんか。
両親は国際結婚してその後離婚をしたので、日本語の世界は父、中国語の世界は母です。空間でのスイッチが多いので、言葉が混ざったりはしないです。
わたしはスペイン語とポルトガル語がごちゃ混ぜになります。母の故郷で私の生まれたペルーはスペイン語で、父の故郷で私も幼少期を過ごしたブラジルはポルトガル語です。国境付近の町などでその2つの言葉が混ざることをポルトニョールといったりしますが、それがわたしの家の中でも起きています。2つの言葉は似ているので、両親はお互いの言葉が分かります。わたしがどっちの言葉で話しても大丈夫なんです。
僕は言葉が混ざらないです。家の中では絶対にネパール語です。僕が小学生のときは、妹は日本生まれで日本の保育園に行っていたので、日本語しか話せませんでした。だから、お互いの言葉がわからなくてよくケンカしました。その後妹はネパールに帰って、日本語を全部忘れたので、今はネパール語しか話しません。
うちは弟が日本で生まれてずっと日本なので、日本語しか話さないです。スペイン語もポルトガル語も一切わからないから、両親と会話ができません。両親は片言の日本語を頑張って話しますが、進路とか何かあるとわたしに言ってきて、わたしが通訳しないといけないです。
複数言語を話せることでの強みやメリット、一方での大変さはありますか

わたしは国際教育学を専攻しているんですが、研究フィールドは自分の原点である台湾の日本人学校です。わたしと同じように親が国際結婚をした子どもに話すとき、中国語でコミュニケーションできるので強みを感じています。日本でも、中国からの移民高校生の仲介に入ったり、中国語を使うことで社会をつなげる役割ができるので、2つの言語を持っていてよかったと思います。
わたしは母から、とにかくスペイン語とポルトガル語を忘れるなと言われて育ちました。言語の数が増えるほど、あなたはより大きな人になれるんだよって。日常会話レベルですが、母語を維持するために頑張っています。
僕の一番のメリットは、できる言語の数だけ、情報収集が倍できることですかね。でも、僕の場合は、母語を維持 "させられている" 部分もあると思います。両親はネパールの言語や文化を叩き込みたがっているけれど、僕個人の考えとして維持しなくてもいいかなと思うんですよね。今、周りでも親の呼び寄せで来日するネパールの子どもが増えているけど、幼少期から日本語もネパール語も、とやろうとすると苦労するのは子ども側なので。母語や文化を教えたいなら、ある程度成長してからでもいいのかなと思う。
わたしもそれはすごく思います。わたし自身も母語を維持しているといっても、高めようとはしていなくて、最低限これ以上は話せなくならないようにとりあえず頑張っているというレベルです。幼少期に来て、2つの言語を中途半端に覚えてダブルリミテッドになる子どもがいるし、それで一番苦労するのは子どもです。同級生の中にも、難しい言葉がわからない子や、文章が書けない子もいました。一つの言語が自分の中で確立するまでは、次の言語を学ばない方がいいのかなと思います。
友達や周りの人に、自分のルーツを知ってほしいと思いますか

複数言語を話せると言語ごとの特徴があるから、別人格の自分がいるみたいな感じがするんですが、この感じ、わかりますか。
そうそう、それはわかる!
いるんですよ、全然違う別人格の自分が。
中国語のゆうこと、日本語のゆうこ。両方持てるからラッキーです。
二人は、友達や周りの人に自分のルーツについて知ってほしいと思いますか。
知ってほしいと思います。やはりわからない部分があるんですよ、日本の文化が。ネパールに戻っていた時期もあって、抜けているところがあります。例えば野球だったり、中学校でやっていたことなど、たまに話についていけないことがあります。そういうことは知らないんだということを理解してもらうのは、いいんじゃないかと思っています。
わたしは外見や話し方で気づかれないので、「昔こういうのが流行ったよね」と昔話をされると「わたしは昔日本にいなかったから知らないんです。実はペルー出身なんです」と言うと、たいていびっくりされます。先に言った方がわかってもらえるので言います。
わたしもサブリナさんに似ていて、自己申告制ハーフと自覚して自分から言っています。9年間日本人学校に行っていたので、日本で何が流行っているかもわかるし、ある程度日本のような生活ができる環境でしたから、言わないと海外育ちだって分からないんです。
もっと多様なつながり方で、日本とつながっている人がいるということを知ってほしいという気持ちで、自分のルーツを話します。
外国につながる若者たちの座談会は、いかがでしたか。今月は「言葉」について話していただきました。
家族の仕事の都合などで国を行き来し、日本にやって来る子どもが年々増えている中で、子どもたちの日本語指導や母語教育についてはさまざまな議論がされています。子どもの頃から異なる言語に揉まれながら育ってきた若者たちの声というのは非常に参考になると同時に、母語とは違う言葉を覚えていくのには、相当な努力が必要だということがわかります。
20代に成長した若者たちは、座談会でしっかりとした自分の意見をたくさん話してくれました。
次回は、「学校・進学について」です。
── 次号へ続く
