集英社MORE ファッション誌だからできること、やさしい日本語で生活を楽しむためのお出かけ情報を発信

集英社が発行するファッション誌『MORE』は、2023年からウェブサイトを通じてやさしい日本語の記事の配信(やさしい日本語 MORE JAPAN | おでかけで日本の魅力発見! | MORE)を行っています。20代の若い女性をターゲットに、ファッションや美容、お出かけ情報を日々発信している媒体でのやさしい日本語活用は、その意外性でも大きな注目を集めました。
今回は、『MORE』におけるやさしい日本語のお出かけ情報発信について、この取り組みを始めた編集者の佐々木真穂さん(元集英社 第7・9編集部 部長)とMORE WEBプロデューサーの花岡美香さんにお話を伺いました。

生活を楽しむためのやさしい日本語があってもいい
――はじめに、MOREについて教えてください。
『MORE』は1977年に創刊されたファッション誌です。MORE WEBは、オリジナル記事中心のウェブマガジンです。どちらも20代の働く女性に向けて、ファッションやビューティー情報などを発信しています。
MORE WEBの中でも人気なのが、日本全国のお出かけ情報を発信するMORE JAPANです。雑誌が45周年を迎えたタイミングでコロナ禍になり、読者世代である20代女性とともに日本を元気にしたいという思いからスタートしました。記事はMOREインフルエンサーズという、読者組織のメンバー中心に執筆しています。
――やさしい日本語の記事を配信するようになった経緯を教えてください。
(佐々木が)数年前に日本語教師の資格を取ったのですが、その勉強をしている時にやさしい日本語に出会い、これは面白い、世の中の役に立つなと思いました。ファッション誌の仕事でも、「こなれ感」や「抜け感」のように私たちにとっては当たり前で便利な表現が、読者にはなかなか伝わらないという悩みがありました。ちょっとした書き換えで受け手に伝わりやすくなるという点で、やさしい日本語は自分の仕事とも親和性が高そうだと興味を持ちました。
やさしい日本語を知ってから、世の中のためになり、なおかつ『MORE』のためにもなることを探しました。やさしい日本語は、誕生のきっかけでもある防災や医療の現場、行政の窓口など、命や生活に密接に関わる分野や場面を中心に広がっていました。そこで、まだあまり取り組まれていない、生活を楽しむための情報をやさしい日本語で届けようと思いました。それこそが、出版社で雑誌を作っている自分にできる取り組みだと気づき、2023年 6月からMORE JAPANの人気記事をやさしい日本語に書き換えて配信するようになりました。

――やさしい日本語記事のターゲットを教えてください。
初級文法の学習を終えた、日本で暮らす『MORE』世代の外国人を想定しています。ですが、敬語や受身、使役などの習得が難しい表現はなるべく避け、できるだけ伝わりやすい文型を使うよう心がけています。その一方で、記事の中のすべての語彙をやさしい言葉に書き換えるのではなく、知っていて生活がより豊かになりそうな言葉は極力残すようにして、学ぶ要素も入れています。例えば「白玉」という言葉も、漢字は小学校1年生で習う漢字なので簡単な言葉に見えますが、日本語の教科書には出てこないので、日本語初級レベルの外国人には知らない方も多いと思います。そこで記事に説明の注を入れたり、MORE WEBの強みである写真などを活用したりして伝わるよう工夫しています。
――ルビのあり・なしも選べるのですね。
立ち上げ当初はシステムの都合で漢字にルビを振れず、漢字の後ろに()で入れ、ふりがな「あり」と「なし」の記事を2本同時に公開していました。その後、記事の右下にふりがなの「あり」「なし」を選べるボタンをつけ、1本公開の今のスタイルに落ち着きました。元記事へのリンクも貼っているので、日本語のレベルによって3種類の表示が選べます。また、九段日本文化研究所日本語学院の留学生のアドバイスも取り入れて、記事の内容がすぐにわかるよう、タイトルの頭にキーワードを並べています。
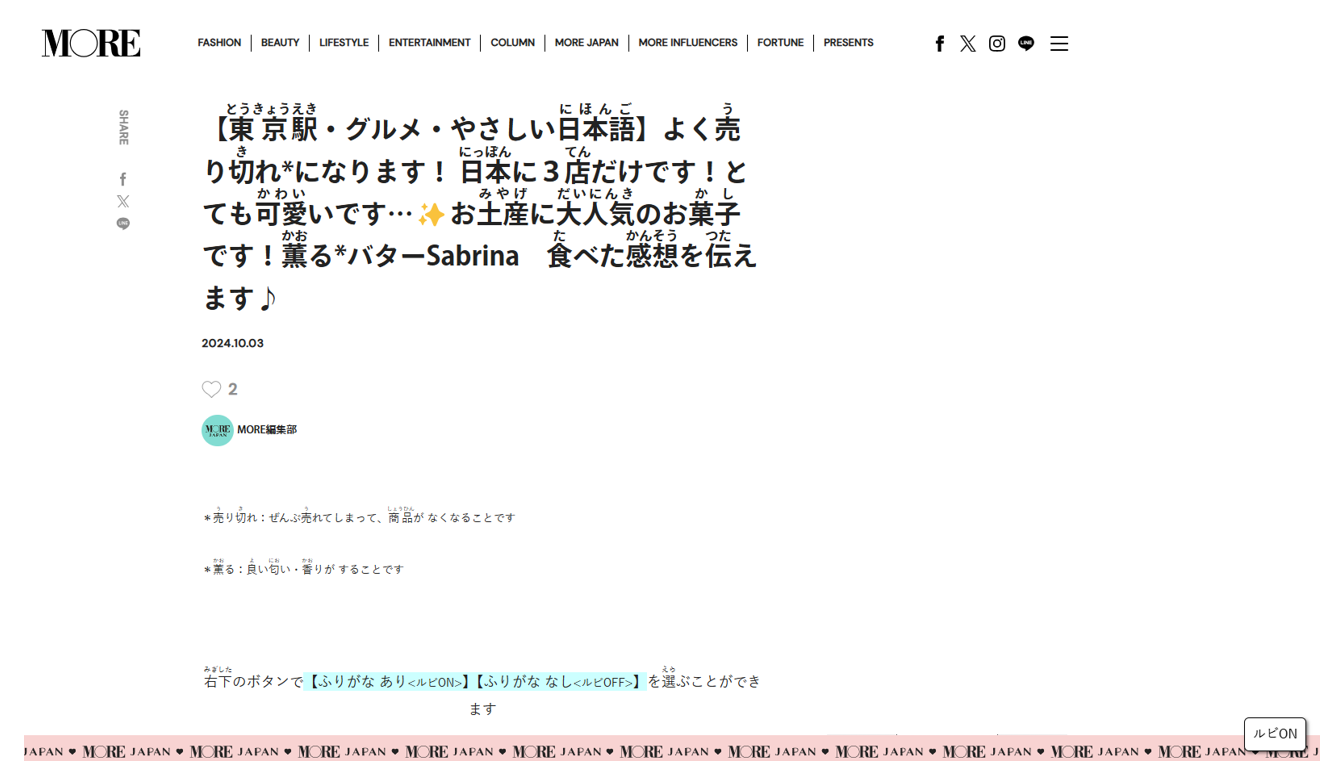
若い世代をやさしい日本語の活動に巻き込んでいく
――やさしい日本語への書き換えはどのように進めているのでしょうか。
現在は4つの大学にご協力いただき、学生にやさしい日本語への書き換えを、先生たちに監修をお願いしています。MORE JAPANの記事を学生にやさしい日本語にして送ってもらい、日本語教師や編集者としての知見から要望を伝え、それを再度検討してもらう流れです。このやさしい日本語化の作業の中では、わかりやすい内容にするため、情報の取捨選択を行います。しかし、学生たちがあえて抜いた箇所こそが、記事としてニュアンスを伝える大事なパートだったりもするので、ここは残したいと説明してリライトをお願いする場合もあります。
――大学生に書き換えをお願いすることになったきっかけを教えてください。
日本語教師の仲間がたくさんいるので、その人たちに頼む選択肢はもちろんありましたが、若者言葉がたくさん出てくる『MORE』の記事だからこそ、若い人の感覚で書き換えてもらった方がいいと考え直しました。加えて、若い世代をやさしい日本語の活動に巻き込んでいくのも重要だと思いました。そこで、日本語教師の仕事や、やさしい日本語の活動を通じて知り合った大学の先生やご紹介いただいた先生たちにお願いをして、日本語教育・多文化共生などに興味がある大学生に参加してもらいました。先生たちからも、「学生にこうした機会を持たせたかった」、「社会との繋がりを作れるのがよい」と言っていただいています。今後もいろいろな大学に参加してほしいので、興味があればぜひ『MORE』編集部に連絡してほしいですね。
――若い世代ならではの視点を感じることはありますか。
例えば「やんごとなき」という言葉を、「お姫さまのように」と書き換えたケースがありました。表現的にはイコールではないのですが、特別なものだ、ということは伝わります。ディズニーの映画やディズニープリンセスに親しんでいる世代ならではの言い換えでいいなと思い、そのまま残しました。
他にも、スイーツを紹介した記事の「悪魔的な魅力」という言葉の書き換えでは、はっとさせられましたね。この言葉には、食べたいけど太ってしまうから食べられない葛藤のニュアンスがある、と学生に伝えたところ、「見るだけで食べたくなります」「とても幸せな気持ちになります」という書き換えが戻ってきました。ルッキズムに敏感で、太る=よくないという考えを嫌う傾向にある若い世代の価値観が、やさしい日本語の書き換えに出ているな、と感じた一例です。
やさしい日本語に取り組むのは、出版に携わる者としての役目
――MORE WEBでやさしい日本語を活用した当初の周囲の反応はいかがでしたか?
社内はまだやさしい日本語を知らない人が多かったので、反応は特になかったですね。記事をやさしい日本語に書き換えれば届く範囲が広がると力説しても反応が薄かったし、直属の上司と部下はこの取り組みの意義を理解してくれたものの、そこから先に話は広がりませんでした。取り組み開始から1年半ほどが経ち、取材を受ける機会も増えると、「個人的に応援しています」や「楽しみにしています」など、ポジティブな声も届くようになりました。
多くの出版社の社員が頭の中で想定している読者は、基本的には日本語の母語話者です。外国人のファンが多い漫画であれば、一足飛びに現地の言葉で翻訳したものを出そう、となります。日本語教育関係の出版社以外は、日本に住む外国人向けの取り組みも殆ど行なっていない。だからこそ、やさしい日本語の記事を作れば、これまでにない新しい読者を獲得できるし、それは出版に携わる者の役目だとも思いました。
――やさしい日本語化を進めるうえで、難しいことや苦労される点を教えてください。
雑誌の記事はカタカナやオノマトペ、主語を抜いた表現や体言止めなどが多く、やさしい日本語への書き換えが難しいという声を学生から聞きました。また雑誌ではワクワク感やリズム感を大事にしていますが、やさしい日本語にしようとするとその部分が難しさにつながってしまう場合もあるので、ニュアンスをいかに残すかも今後の課題です。
――やさしい日本語の取り組みを始めて、よかったと感じられたことはありますか?
「生活を楽しむためのやさしい日本語は初めてで嬉しい」という感想や、外国人を支援する方からお褒めのメールが届くなど、好意的な反応をいただいています。またお付き合いのある会社でもワークショップをする機会ももらえて、キャラクターショップの店長などが、やさしい日本語を学んだことで自信を持って外国人にも接客できるようになったと喜んでいました。
――最後に、今後予定しているやさしい日本語での取り組みや意気込みを教えてください。
日本社会で生活する中で、日本の若者たちと同じようにいろいろなところに出かけたり、流行を追ったりしたいと思っている外国人もいるはずです。そうしたときに、日本語力にかかわらず情報にアクセスできたらいいですよね。MORE JAPANのやさしい日本語の記事が、そんな風に生活を楽しむためのちょっとしたヒントになっていったら嬉しいです。
またMORE JAPANでは、今は日本の方が書いた記事を配信していますが、ゆくゆくは、留学生や日本にお住まいではない方の書いた記事も出していきたいです。多文化共生の試みとして、MOREのInstagramでも、留学生 3 名に発信を始めてもらいました。日本に住んでいる外国人だけでなく、海外で日本語を勉強している外国人に「日本に来たい」と思ってもらうきっかけも作れたらいいですね。
