NHK『NEWS WEB EASY』 やさしい日本語をユニバーサルサービスとしてのインフラに

※この記事は、2023年11月に取材した内容にもとづいています。『NEWS WEB EASY』は、2024年9月30日からラジオとウェブサイトで伝える『NHKやさしいことばニュース NEWS WEB EASY』になりました。
日本に住んでいる外国人や子どもなどを対象に、ニュースをわかりやすい日本語に書き換えて配信している『NEWS WEB EASY』。NHKのニュースサイトのコンテンツのひとつとして、やさしい日本語のニュースを発信しています。
「報道機関として、やさしい日本語によるニュースの提供を始めたのは、NHKが最初です。2012年4月に試験公開を開始、翌2013年2月から本公開をスタートしました。10年以上にわたり、やさしい日本語でコンスタントにニュースを発信し続けている唯一のサービスということになります」
そう話すのは、NHK報道局ネットワーク報道部チーフ・プロデューサーの新本貴敏さん。NHKがやさしい日本語でニュースを提供するサービスを始めた背景には、1995年の阪神・淡路大震災があったそうです。
「このとき、日本人に比べて、在住外国人の死傷者の割合が高かったことなどから、災害時の外国人への情報提供が問題となりました。英語での発信が必ずしも有効というわけではないなかで、できるだけ多くの外国人に情報を届ける手段として注目されるようになったのが、やさしい日本語でした。NHK放送技術研究所でも研究が行われるようになり、そのアウトプットとして、2012年にやさしい日本語によるニュースの提供を始めたのです」
やさしい日本語で日本の“今”を知ることができる記事を配信
現在、『NEWS WEB EASY』では、一日に4本、やさしい日本語の新着記事をアップしています。NHKが日々、発信しているたくさんのニュースのなかから、在住外国人が主たる対象であることを意識しつつ、社会的に重要なニュース、世の中の関心が高いニュース、日本各地の表情が伝わるニュースなどを選んでいるそうです。

記事のテキストには、ふりがながふられているほか、人名・地名・組織名称といった固有名詞の色分けも。また、少し難しい言葉にはアンダーラインが引かれており、カーソルを合わせると辞書の説明が表示される機能もついています。ふりがなや固有名詞の色分けは、ON/OFFが可能となっており、それぞれのレベルに合わせてニュースを読むことができます。さらに、音声データや、書き換える前の普通の日本語の記事へのリンクも掲載されており、さまざまな方法で活用できることから、国内外で日本語を学ぶ教材として広く使われているそうです。
「『NEWS WEB EASY』の記事は初級レベルの方でも読めますし、中級以上のレベルの方なら、しっかり理解することができます。時事ネタやタイムリーな話題を通して日本語を学べる貴重な材料であることからも、教材として評価されているようです」
過去記事の語彙の変換データを翻訳システムに蓄積、記事制作を効率化
やさしい日本語の記事制作は、ニュースデスクの経験者である「専門委員」や豊富な経験をもつ日本語教師などが連携しながら進めています。交代制でそれぞれ何人も携わっていますが、一日に稼働するのは、専門委員1人、日本語教師2人、デスク1人、計4人によるチームです。
『NEWS WEB EASY』の新着記事の数が一日4本なのは、一つの記事を完成させるまでに数時間を要するから。作業はまず、前日までのニュースから、やさしい日本語にするニュースを選び、内容を要約するところから始まります。
「基本的な流れを説明しますと、初めに、専門委員が元のニュースのエッセンスを絞り込みながら、短く読みやすい原稿を作っていきます。どんなに長いニュースでも、目安はだいたい350字程度。これを、NHK放送技術研究所が開発したやさしい日本語の翻訳システムにかけて、機械的に言葉を変換していきます。そして、ここから日本語の先生が、よりわかりやすく、やさしい表現へと整えていくのです。システムの画面上に難しい言葉は赤やオレンジで、やさしい言葉は青や緑で表示されるので、できるだけ赤を減らすことを意識して作業を進めます」
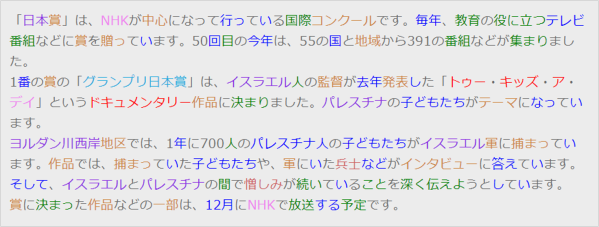
「このシステムは発展途上で、もっと多くのデータを学習させることが必要です。今は、いったんシステムで変換したうえで、どういう言葉に置き換えればより伝わるかを、人が考えながらやっている部分が大きい。もともとニュース原稿には正解がなく、それをどうやさしい日本語にするかについても正解はありません。日本語の先生方がおふたりでいろいろと相談しながら作業を進めてくださっています」
短くても、やさしくても、ニュースの本質を伝える記事に
日本語教師が仕上げた原稿は、デスクが客観的にチェックします。簡単な言葉に置き換えすぎて全体の意味が変わっていないか、大事な情報が抜け落ちていないかなどを確認するのです。

「そのニュースで最も大切なことを伝えるために、多少難しい言葉を残さなければならないこともあります。単にやさしくするのではなく、本質的な意味を伝える言葉を探り、そのニュースの本質を伝えること――それが、『NEWS WEB EASY』がいちばん大事にしていることなのです」
たとえば、昨年の11月に掲載された、パレスチナの子どもたちを追ったドキュメンタリーが国際コンクールでグランプリを受賞したというニュースでは、元の記事にあった「イスラエルとパレスチナの間で続く憎しみの連鎖の背景に迫ろうという作品です」というテキストを、次のように言い換えました。
「イスラエルとパレスチナの間で憎しみが続いていることを深く伝えようとしています」
“背景に迫る”という難しい表現を、“深く伝える”として、答えを見つけることが難しい問題について伝えようとしている作品だということを表したのです。
短くしようとも、やさしくしようとも、ニュースの本質を伝えることにしっかり責任をもつ――報道機関としての矜持を感じさせられます。
やさしい日本語をどこでも誰でも利用できるユニバーサルサービスに
『NEWS WEB EASY』がスタートしてから10年が経過した今、NHKは組織全体として、やさしい日本語の取り組みを強化しようとしているそうです。

「日本に住む外国人の数はますます増加し、社会の中でより大きな存在となってきました。災害時に外国人が取り残されがちだという問題意識なども共有され、やさしい日本語の重要性は増しています。NHKとしても、まだまだ取り組めることがあるはずです」
先のことになりますが…と前置きしながら、新本さんが今後の計画をひとつ、教えてくれました。
「数年以内にやさしい日本語のラジオ放送が実現できるよう検討を進めています。今は前日までのニュースをやさしい日本語にしてサイトで公開していますが、もう少し早く、最新のニュースをやさしい日本語でお伝えすることができないかと考えているんです」
やさしい日本語というものがもっている力、可能性は大きいと新本さんは言います。
「外国人だけでなく、子どもや高齢者、障害のある方にとってもわかりやすいやさしい日本語は、広い範囲の人たちに対するコミュニケーション手段となります。日本社会を支えるインフラとしてやさしい日本語を発展させ、どこでも誰も利用できるユニバーサルサービスにしていきたい。それにはNHKのさまざまな部署が連携して大きな体制で臨んでいく必要があると考えています」
報道機関のなかでもやさしい日本語活用のトップランナーであるNHKが、今後どんな取り組みを進めていくのか、とても楽しみです。
