名古屋市立大学看護学研究科 保健医療現場でのコミュニケーションを担う看護人材にやさしい日本語を

保健医療の現場では、日本語を母語としない人たちとコミュニケーションする機会がますます増えています。そこで注目を集めているのが、「やさしい日本語」です。通訳や自動翻訳機とともに、言葉の壁を低くする手段のひとつとして活用され始めています。
「やさしい日本語は、阪神・淡路大震災をきっかけに、日本語に不慣れな外国人への情報伝達手段として生まれました。防災や行政などの分野で広く使われるようになっていますが、保健医療の分野では、まだあまり知られていません」
そう話すのは、名古屋市立大学大学院看護学研究科の樋口倫代教授。近い将来、医療や地域保健の現場において、患者とのコミュニケーションの最前線に立つ看護学生に、やさしい日本語を教えています。
樋口さんは長らく東南アジアにおける、「健康関連資源へのアクセス」を研究課題としていました。資源の限られた環境にいる人たちが、病院・クリニック・保健サービスなどを利用できているか、健康に関する情報にアクセスできているかなどの研究を続けてきたのです。
その後、縁あって愛知県の名古屋市立大学で勤務するようになった樋口さん。愛知県は外国人住民が多く、保健医療へのアクセスに問題を抱えた人が少なくないことを知ります。
「当事者の声で知ったというより、外国人住民の支援をしている方たちから話を聞いたんです。やはり言葉の問題が大きいと。そして言葉の壁を低くする手段のひとつとして出合ったのが、『やさしい日本語』でした」
樋口さんは、大学でやさしい日本語の研究を始めます。看護学生を対象にやさしい日本語の講義を行い、講義の前後で、知識や書き換えのスキル、そして日本語を母語としない人たちとのコミュニケーションについての認識がどう変化するかを調べることにしたのです。
やさしい日本語の講義・演習を通して学生たちが得た気づき

保健医療分野でやさしい日本語を運用する能力を上げるにはどういう教え方が適しているのかを探り、日本語を母語としない人たちへの健康支援を向上させること――それが樋口さんの研究の目的です。2019年度に参加者を募るかたちでワークショップを実施。翌年度からは、担当する必須科目の1コマに、やさしい日本語の講義・演習を取り入れるようになりました。
講義は1コマ90分。最初と最後に5分ずつ、効果を検証するための質問票に回答してもらう時間を取るので、実質は80分です。スライドと資料を使った説明に25分、単語や短文の書き換えを行う個人ワークに20分、少し複雑な長文の書き換えを行うグループワークに15分、書き換えた文章と工夫した点・難しかった点などの共有に15分、まとめに5分という流れで進みます。教材として使用しているのは、出入国在留管理庁と文化庁が共同で作成した『在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン』と、愛知県が発行している『「やさしい日本語」の手引き』です。
この講義でやさしい日本語を初めて知る学生も多いそうですが、講義の前後で学生たちにどのような変化が見られるのでしょうか?
「伝わりやすくする工夫として、『難しい言葉を置き換える』『漢字にルビをふる』といったことをイメージできる学生は、講義の前にも一定数います。講義後に増えるのは、『情報の中から必要なものを取捨選択する』『余分な情報をカットする』『ひとつの文の中では、ひとつの情報提供にとどめる』といった回答です。平易な語彙を用いたり、ルビをふったりすることだけがやさしい日本語ではない――こうした気づきを得られるのは大きいと思います。また、やさしい日本語について肯定的な回答をする学生の数も大きく増えました」
保健医療分野でのやさしい日本語の活用は、その限界を知ることが大切

保健医療アクセスを改善するための研究にともに取り組んでいます
保健医療の現場で医師など他職種と患者の間をつなぐ役割を担うことが多い看護職。ケアの最前線に立って日々、患者と接する仕事のため、看護教育ではもともと、コミュニケーションスキルを身につけることが重視されてきたそうです。つまり看護学生には、「どうしたらわかりやすく伝えられるのか」を考える意識が、すでにインストールされているということ。日本語を母語としない人とのコミュニケーションツールである「やさしい日本語」を知った学生の多くが、「これは使える!」「高齢者やお子さん、障がいのある方にもいいですね」といった肯定的な反応を見せるそうです。
「ワークの面白さや、物珍しさもあるのだと思います。いろいろな気づきを得てくれることはうれしいですが、やさしい日本語を肯定しすぎていて、不安になることもあります」
やさしい日本語は決して万能でないことを知ってほしいと、樋口さんは言います。
「特に保健医療分野での活用については、医療用語にまでやさしい日本語を使うかなど、議論を深めていくことが必要です。知識やスキルの習得と併せて、その限界を認識してもらうこと。これが、保健医療従事者にやさしい日本語を教える際の重要なポイントだと思います」
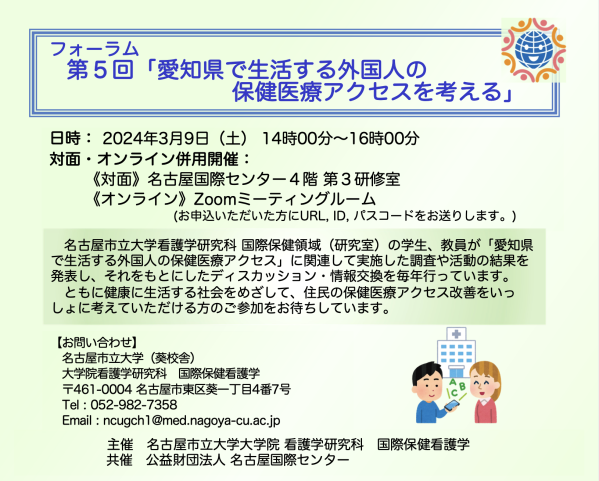
保健医療の現場では、生命に関わる情報を正しく伝える必要があります。そのため、日本語を母語としない人とのコミュニケーションにおいて理想とされるのは、保健医療従事者とトレーニングを受けた医療通訳者が連携することです。医療用語はもちろん、秘密保持などの医療倫理をしっかり理解している通訳者が入るのがいちばんなのです。
けれども医療通訳は、予約制になっていたり、言語によっては対応できる人が少なかったり、費用負担の問題もあって、いつでも利用できるわけではありません。
「重要な場面ではプロの医療通訳を活用しつつ、日常のケアにおいては、やさしい日本語と機械翻訳を併用するというのが今後の道ではないでしょうか。これらをどう組み合わせて使えるかが、看護師に必要なスキルになっていくと思います」
樋口さんは今後、やさしい日本語の講義に機械翻訳の演習も取り入れる予定だそうです。やさしい日本語で話すことは、機械翻訳の精度を上げることにも役立つのです。
「日本語は、主語や述語を抜いて話すことが多いですよね。そのあたりを意識せずに自動翻訳機に向けて話すと、いい翻訳結果が出ないんです。機械翻訳できちんと正しく翻訳されるような日本語を話すトレーニングが必要だと思います」
医療通訳者を介するにしても、機械翻訳を利用するにしても、やさしい日本語で話すにしても、目指すところは正しい情報に到達してもらうこと。大切なのは、場面によってコミュニケーションの手段を使い分けることなのです。
やさしい日本語を保健医療の現場へ

さまざまな国の文化を理解するための授業も担当しています
将来の保健医療従事者である看護学生を対象に、やさしい日本語の教育に取り組んできた樋口さん。保健医療の現場にやさしい日本語を普及させたいと、今さまざまな働きかけを行っています。
「新たな試みとして、大学病院の協力のもとで、看護師さんたちにやさしい日本語を伝えていくことを計画しています。また、保健センターの保健師さんたちを対象とした研修にやさしい日本語を取り入れてもらえないか、名古屋市の担当部局に相談しているところです」
医療現場はもちろん、保健サービスの現場でも、日本語を母語としない人たちへの対応が求められるようになっています。樋口さんが以前、愛知県内の市町村の保健関連部局を対象に実施した調査でも、何に困っているかという質問に対し、「日本語を母語としない人へのサービスの提供に課題を抱えている」という回答が多く見られたそうです。
「名古屋市立大学でも、新しいカリキュラムで『多文化健康支援看護学実習』が必修となります。やさしい日本語と機械翻訳を併用すること、この2つの組み合わせの限界を知ること、日本人が忘れがちな文化的背景や宗教的背景に対する配慮の必要性——こういったことを教育や研修に組み込んで、保健医療に関わる人たちに伝えていきたいと思います」
日本語を母語としない人たちが平等に保健医療にアクセスできる社会を目指す樋口さんの取り組みは、まだまだ続きます。
