クローズアップ
特定非営利活動法人 防災コミュニティネットワーク ~防災をきっかけに広げる地域のつながりの輪~

東京都内のさまざまな地域で防災教育事業や防災コミュニティ事業などを展開しながら、地域住民の共通の課題である防災を通じたコミュニティの形成を目指す「防災コミュニティネットワーク」。防災の視点を取り入れた地域清掃活動や街歩き、非常食を使った子ども食堂など「身軽に、気軽に、楽しく」参加できる防災活動をさまざまな地域で行っています。団体の設立者の一人である宇都貴博さんにお話を伺いました。
地域づくり×防災というアプローチ
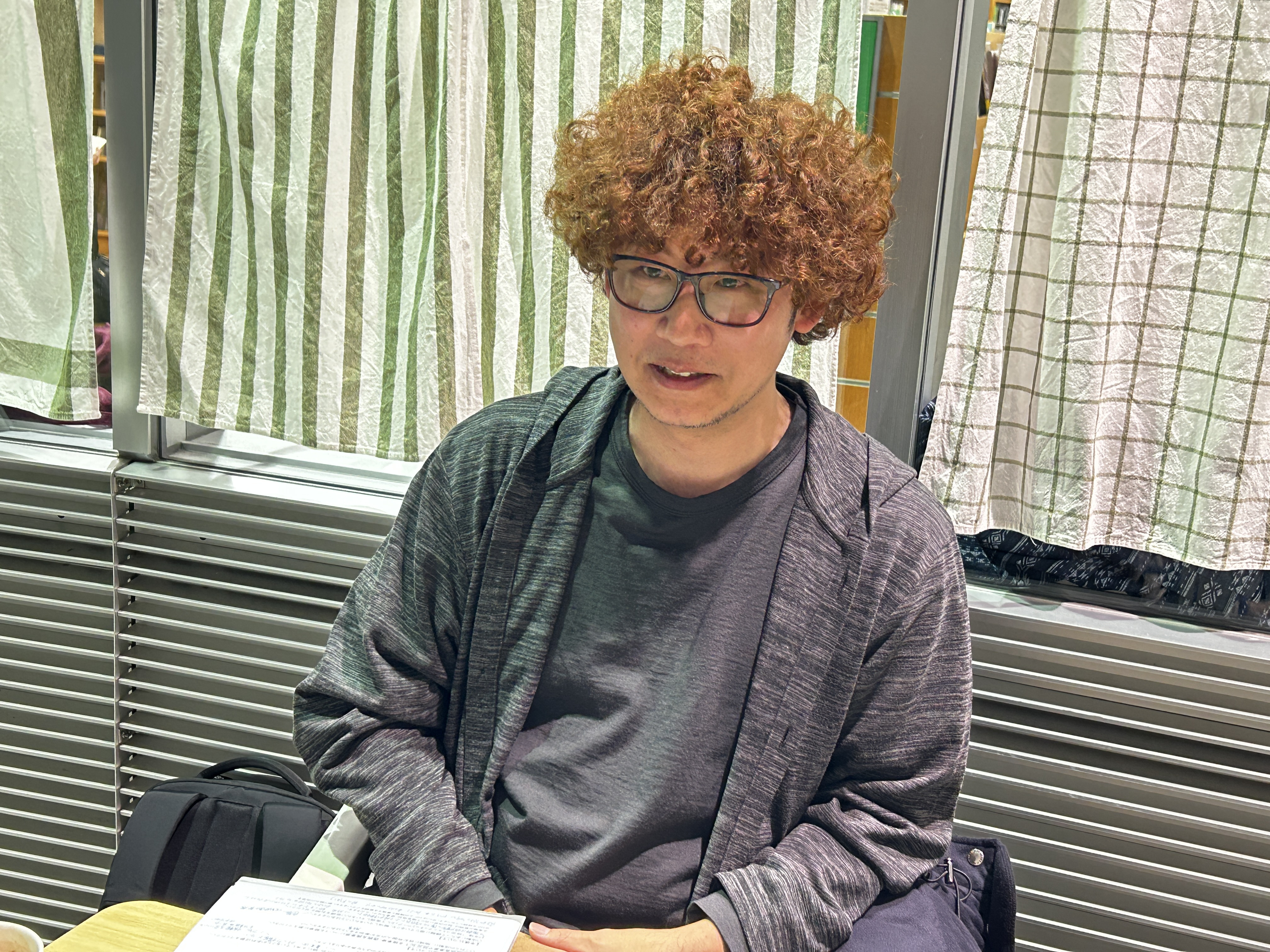
防災コミュニティネットワークは、防災コミュニティ事業・防災ICT(情報通信技術)支援事業・防災教育事業・復興支援事業の4つの柱の中で様々なプログラムを実施しながら、防災活動をとおしたコミュニティの形成とそのネットワークの構築に力を入れています。大学院で政策学の一環として地域づくりを共に学んだ理事長の増村一樹さんと宇都貴博さんが、地域づくりの手段として着目したのは、防災でした。
「防災は、年代や国籍を問わず、すべての地域住民が共通して抱えている課題です。そして、いつ起こるかわからない災害に対する最大の備えは、人と人のつながりだと私たちは考えています」と、宇都さん。
防災を絡めた地域づくりを行っていくため、2018年に団体を設立、2019年にNPO法人にしました。現在団体としては4名を中心に、10名程のメンバーで活動しています。「レッツボウサイプロジェクト」として、身軽に、気軽に、楽しく様々な防災体験を通して防災関係人口を増やすことで、強いコミュニティ形成の実現を目指します。
情報弱者を減らし、自助の力を高める

写真提供:防災コミュニティネットワーク

写真提供:防災コミュニティネットワーク
団体として最初に取り組んだのは、情報弱者になりやすい外国人留学生への防災教育でした。理事長の増村さんが勤めていた品川区にある外国人留学生の学習支援塾で、「この前の地震、大丈夫だった?」と留学生に聞くと「怖かった。地震について何も知らないことが怖い」という答えが返ってきたことがきっかけだったといいます。
「日本では小学校などで地震や災害について学びますが、地震のない国で生まれ育った外国人の中には『地震が来る』とニュースやアプリで見ても、どう対応するべきか分からず、不安を感じている人も多いです。机の下に隠れる、火を消す、ドアを開けるなど、日本人が自然に行うような災害における基礎情報を伝えています」と、宇都さん。
また、ICTの部分で情報弱者が生まれないよう、ICT支援事業にも力を入れています。東京都防災アプリや自治体の提供する防災アプリの活用方法を学ぶ講習会や、シニア向けにはスマートフォンを使った災害情報の入手と活用方法を学ぶ講座を開催し、今では年間1,000人以上の方が受講しています。
「もともとは行政と福祉の繋がりを知るために高齢者福祉施設で働き出したことがきっかけだったんです。コロナ禍で施設は閉館していたものの、『ワクチン接種の申込方法が分からない。電話も繋がらない』という相談が相次ぎました。一人ひとりに教えていると、そもそもスマートフォンの電源の入れ方や音量の上げ下げの仕方を知らない方も一定数いることに気がつきました。情報弱者を減らすことは、防災にも繋がります。今では防災アプリだけでなく、決済アプリでの支払いを行えるようになったシニアの方もいます」と、宇都さん。
防災をきっかけに生まれる地域住民のコミュニケーション

写真提供:防災コミュニティネットワーク
防災コミュニティネットワークでは防災における「自助」だけでなく、「共助」にも重点を置き、防災コミュニティ事業として展開しています。
特に人気が高いのが、自治体や町会から依頼を受けて行う「防災まち歩き」です。防災視点で近所の危険な場所や防災に関する表示などを確認しながら、まち歩きをします。地域清掃と組み合わせて行うこともあるといいます。
「町会などから、『町内に外国人コミュニティが何年も前からあるけれど、声をかけにくい。何か話すきっかけが欲しい』といった相談が来ることもあります。依頼があった際には、まち歩きなど、できるだけ年代や国籍を問わず誰でも参加しやすいイベントを企画するよう、心掛けています」。
依頼元と相談しながら、イベントのやさしい日本語のポスターを作成して配布したり、外国人のキーパーソンにアプロ―チをしたりすることもあるといいます。過去には、インド出身者たちが毎朝お祈りをする小さなインド寺院に通い、やさしい日本語で書いた街歩きのポスターを配ったこともあったそうです。
「普段なかなか接する機会がなかったとしても、災害が起こった際には、日本人も外国人も関係なく協力し合わなければいけません。まち歩きなどのイベントの中では、双方向のコミュニケーションを促せるよう、毎回工夫しています。外から来た我々ができるのはあくまでもきっかけ作りなので、その後につなげられるかどうかだと思っています。イベント後に、実際に地域の外国人と日本人で一緒に餅つき大会をした、とか、今度は自分たちで外国人に声をかけて避難訓練を実施する、といったご報告を受けるとやっぱり嬉しいですね」と、宇都さん。
いざという時の共助のために、顔の見えるつながり作りを

写真提供:防災コミュニティネットワーク
「地域で活動をしていくと、その地域やそこに住む一人ひとりが抱える課題が表面化すると感じます」と、宇都さん。地域には「災害時要援護者」と呼ばれる、災害発生時の避難などに支援を必要とする方々も暮らしていますが、地域コミュニティが希薄化することでそうした方々がどこに住んでいるか、周囲に住む人も把握しにくくなっているという現状があります。
防災まち歩きに視覚障害をもつ人が参加した際、まち歩きの後のグループワークの中では「どのように視覚障害をもつ方の避難を助けられるか」という話し合いも行われました。終了後、視覚障害をもつ参加者は「対応しきれないような大災害が起こったら、自分は死ぬしかないと思っていた。でもまち歩きに参加して、みんなの話を聞いていて、“生きろ”と言われているように感じた」と語ったそうです。
「災害が起こってからではなく、起こる前から地域でそうした課題に向き合って、一緒に考えることが大切だと思います」。
いざというときに助け合えるコミュニティにするべく、顔の見える関係づくりのために台東区で行っている活動の一つが、「ボウサイみんなの食堂(子ども食堂)」です。提供する食事の中に非常食を織り交ぜることで、非常時に初めて非常食を食べるのではなく、普段から親しめるようにしています。気軽に参加できるよう、漢字ではなく「ボウサイ」としているそうです。実際に、子どもからお年寄りまで、さまざまな年代の地域の人が集う居場所になっています。 「子ども食堂で会話をし始めると、良い意味でお節介が始まります。近所に住むウクライナ避難民の子も、学校になかなか馴染めず、『居場所がない』とここを利用してくれたんですが、ここでは学生ボランティアと交流したり、勉強を教えてもらったり、町の人の紹介をきっかけに、今は空手クラブにも入りました。そうやって少しずつ一人ひとりの居場所が広がっていくと良いなと思っています」と、宇都さんは話します。
自発的に活動が行われるコミュニティ作りを目指して

写真提供:防災コミュニティネットワーク

写真提供:防災コミュニティネットワーク
防災をもっと身近なものとして感じてもらうために、団体として注力している活動の一つが、「レッツボウサイフェス」です。マンションの駐車場などを借り、放水訓練や地震のVR体験、地域清掃などを行います。訓練や清掃に参加すると、ヨーヨー釣りやくじ引きができるチケットをもらえることもあり、子どもたちも楽しく参加することができます。
「一番盛り上がるのはバケツリレーです。年齢も国籍も関係なく、町のみんなでバケツを運び、タイムを競います。東京の路地裏で、みんなでバケツリレーをしたら楽しいだろうな、と思いついたことから、ボウサイフェスを企画しました。”レッツボウサイ”と親しみやすいような名称にしたり、子どもも楽しめる工夫をしたりすることで、みんなが一体となり、楽しみながら防災ができる機会になっていると思います」と、宇都さん。今後も開催箇所を増やしていくことを目指しています。
さまざまな活動を精力的に行う防災コミュニティネットワーク。今後は防災を通したコミュニティ作りのさらなる展開を目指します。
「防災を介したコミュニティづくりを、我々だけでなく、誰がやっても面白くなるような仕組みにして展開していくことで、さまざまな地域に拡げていきたいですね。地域の人たちや、活動に賛同してくれるボランティアサークルの人たちと連携しながら、人材育成も進め、ゆくゆくは若い大学生の人達にも活動を任せていけるようにしていきたいと思います」と、宇都さんは語ります。 多くの若者や外国人、高齢者と多様な人が参加する防災活動の輪は、少しずつ広がり始めています。
*本記事は取材時点での情報をもとに作成しています。最新の情報については、団体へ直接お問い合わせください。
