クローズアップ
Yangonかるたプロジェクト ~ミャンマーの"今"を知らせるために、平和で美しい日常を伝える~

「もっとミャンマーのファンを増やしたい」。そんな思いから、野中優那さんが立ち上げたのが「Yangonかるたプロジェクト」です。なぜ日本に住む高校生が、ミャンマーを好きになってほしいと考え、団体を立ち上げたのでしょうか。野中さんに、プロジェクトに込めた思いや背景など、詳しくお話を伺いました。
当事者でない人々が理解したとき、世界は動く

「Yangonかるたプロジェクト」が立ち上がったのは2021年3月。ミャンマーでクーデターが起こってから、わずか1か月後のことでした。
「親の仕事の都合で、私は2019年から家族でミャンマーのヤンゴンに住んでいました。クーデターが起こったときも、ヤンゴンにいました。朝いつものように起きたら父からクーデターが起こったことを告げられ、今まで送っていた日常や平和な町が突然変化したことに、大きな衝撃を受けました。夜はインターネットが遮断され、朝になると、国内各所で起こった悲惨な状況のニュースが飛び込んできます。毎日、朝が来るのが怖かったです。一方で、混乱の中でも、歌を歌ったり、警察官に花を渡したりなど、平和的なデモを行うミャンマーの人たちの姿には、深く感動しました」。
当時、高校進学のために日本に帰ることが決まっていた野中さん。ミャンマーの情勢を気にかけながら、その後まもなく家族で日本に帰国しました。日本に帰ってから感じたのは、大きな違和感でした。
「『最近までミャンマーで暮らしていた』と話すと、『内戦しているところだよね。危ない国から帰ってこられてよかったね』と声をかけられることがありました。ミャンマーは、豊かな文化を持つ、美しい国です。そしてクーデターで日常を奪われたのは、日本で暮らす私たちと何も変わらない、普通の人たちです。なぜみんな、こんなに無関心で他人事なんだろうと思いました。しかし振り返ってみると、これまで他の民族の問題に無関心だったのは私も同じです。ミャンマーの問題を、多くの人に『自分ごと』として考えてほしい。当事者でない人々が理解したときに、世界は動くのだと信じています。そんな思いから、兄と弟と一緒にプロジェクトを立ち上げることにしました」。
「かるた」遊びを通して、ミャンマーのファンを作る

ミャンマーを伝える手段として「かるた」を選んだのは、「学びの中にも、遊びは必要」という野中さんの気づきによるものです。
「帰国後、街頭でミャンマーの募金活動をしたのですが、町を歩く人から腫物のように見られた印象がありました。悲しい情報だけでは、なかなか伝わらない、覚えてもらえないと感じました。だから逆に、ミャンマーの魅力を発信することにしました。ミャンマーのファンになってもらえれば、自分から能動的に情報を探す人も増えてきます。幸い、ヤンゴン滞在中に、私と家族は町の風景をたくさん写真に収めていました。その写真を使って、小さい子どもからお年寄りまでみんなが楽しくミャンマーについて知ることのできる『かるた』を作ろうと考えました」。
「かるた」を作る際は、実際に住んでいる人の暮らしや、息遣いが伝わるように思いを込めました。たとえば、札の中にある「うまれかわる裏路地 ヤンゴンウォール」は、Instagramでも人気のスポットを切り取った一枚です。「ゴミであふれた裏路地を清掃し、若いアーティストが壁に絵を描いたのがヤンゴンウォールです。美しく彩られた路地は、ゴミが捨てられなくなり、若者の憩いの場になりました。ヤンゴンにこんな素敵な場所があることを、多くの人に知ってほしいです」と野中さん。
有識者と校正を重ね、クラウドファンディングで「かるた」を制作

「Yangonかるた」の制作は、さまざまな人の力を借りながら進められました。
「素案は私が作りましたが、ミャンマー語をカタカナに直したときの表記に不安がありました。専門的な見地から校正をお願いするために、大学教授や、通訳者など、さまざまな方に連絡を取り、ご協力をお願いしました」。
そして野中さんが「表記の問題以上に難しかった」と話すのは、文化的な側面の検証です。ミャンマーは135の民族が住む、多民族国家です。さまざまな民族の人の背景や心情にどこまで配慮するか、悩んだこともあったそうです。
「たとえば『カチン、カレン、カヤー、チン、モン、シャン、ラカイン、ビルマなど、多民族国家』という札は、ミャンマーで8大民族と言われる8つを紹介しています。それ以外の民族にも配慮して、もっとたくさん挙げるべきかな、とも思いました。でも全部を紹介していたら、わかりにくくなってしまいます。悩みながら、最終的にはかるたで遊ぶ日本人の観点から、わかりやすさを優先することにしました」。
4か月間、校正に校正を重ね、原稿が完成。「Yangonかるた」の商品化にあたって、野中さんはクラウドファンディングを実施することに決めました。
「最初は、全然頭にない発想でした。ですが、ミャンマーの日本人学校の先生から『クラウドファンディング自体が、ミャンマーを知ってもらう手段になる』と勧められて、興味を持ちました。色々な人に情報を届けるために、クラウドファンディングのページはすごく頑張って作りました」。
野中さんの努力が実り、目標金額150万円は2週間で100%を達成。最終的に300万円を超える寄付が集まりました。
「私自身に力はない」。だからさまざまな人と一緒にミャンマーを伝える


団体を立ち上げてから、「Yangonかるたプロジェクト」が実施したり、参加したイベントは実に40以上にのぼります。
野中さんが企画するイベントには、さまざまな工夫が凝らされています。かるたを紹介するときは、現地で撮影した動画や写真を投影し、ミャンマーの風景を見てもらいます。またクーデターでミャンマーの人たちの身に起こっていることについては、ただ言葉で説明するだけでなく、イラスト付きのカードを「ガチャ」として参加者に引いてもらうようにしました。これらは、もしミャンマーに住んでいたら明日起きるかもしれないこと。紙を開くと広がる凄まじい現実に、参加者からは驚きの声が聞かれます。
イベントの多くは、さまざまな人や団体とのコラボによって開催されています。コラボイベントを企画する背景には、ある思いがあるそうです。
「私にはコネクションも人脈もなく、『私自身に力はない』と思っています。力がないから、誰かの力を借りるしかありません。だからクラウドファンディングのときも、返礼品にミャンマーの輸入雑貨店の商品を購入し、ショップの方に広報を協力してもらいました。イベントも、カフェやレストラン、写真家の方など、さまざまな方と協力して開催しています。誰かと協力すると、力が "足す" ではなく、"かける" になって、倍以上になる。そんなふうに感じます」。
マイノリティの立場が守られる社会の実現のために

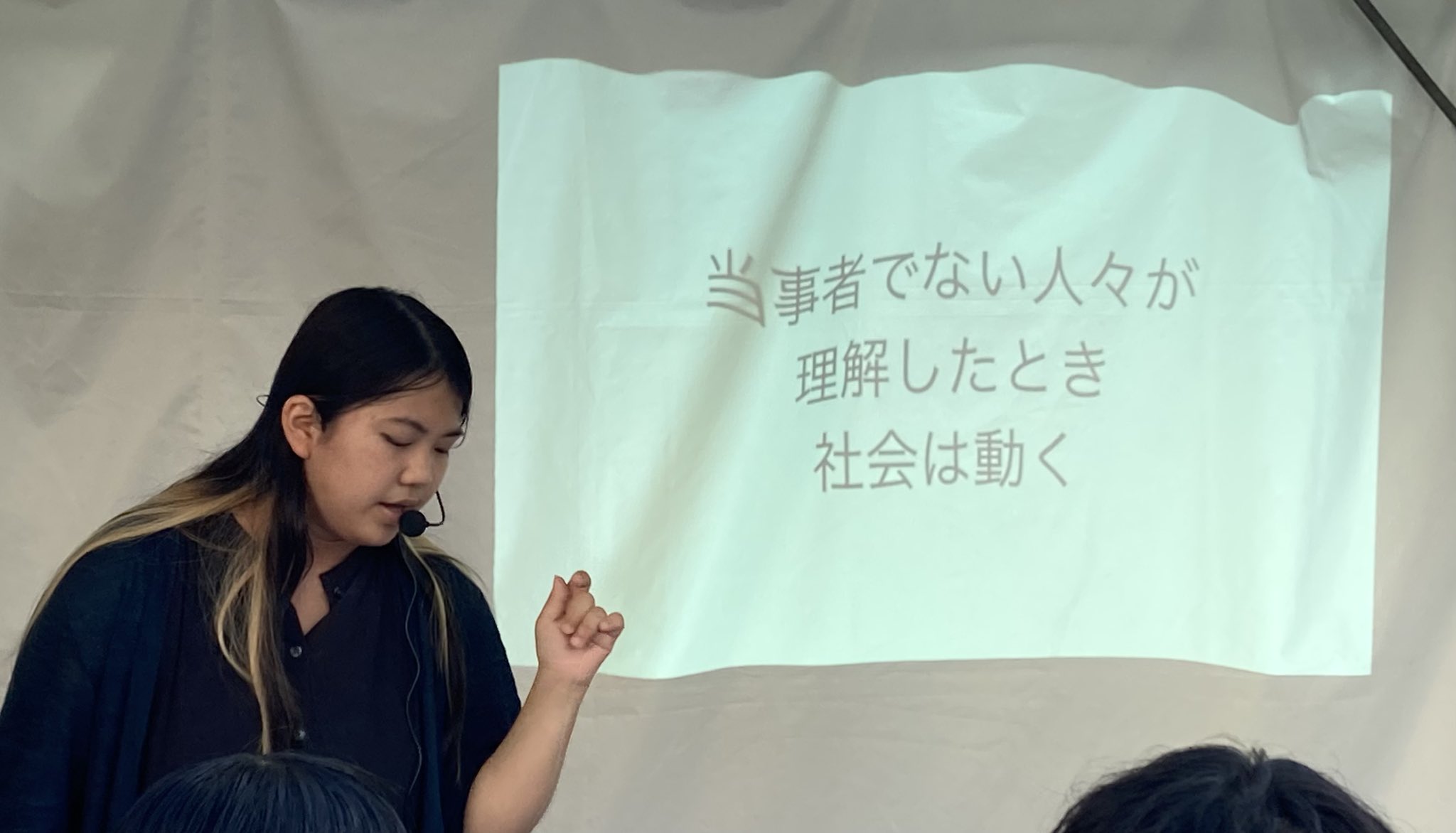
野中さんが始めた活動は、さまざまな広がりを見せました。
「『ウクライナのニュースを見るたび、ミャンマーを思い出すようになった』と言ってくれた同年代の子がいました。とてもうれしいです。ミャンマーの平穏な日常とクーデターの惨状、両方を伝えるから、コントラストがあって印象に残るのかなと感じます。また、ミャンマーにルーツを持つ日本在住の子供から、『ミャンマーのことを知ることができてよかった』という反応をもらったこともありました。思いもよらない反響でしたね」。
活動の中で、日本とミャンマー以外の地域の人とつながりを持てたことも、当初は予想していなかったことでした。「自分が実情を知らなかった地域や民族の人と知り合う機会がありました。世界にはさまざまな紛争・問題があることを知りました」と話す野中さん。今後、国境を越えた取り組みにも興味があるそうです。
「世界の紛争、そして平和について考える企画を実施してみたいです。ミャンマーの人たちのように、いつ自分が紛争の当事者になるかはわからない。そうした当事者、マイノリティの人たちが守られる社会であってほしいと思います。そのために、大学で法律などの勉強も続けながら、今後も活動を広げていきたいです」。
強い思いとともに、野中さんは活動を続けていきます。
*本記事は取材時点での情報をもとに作成しています。最新の情報については、団体へ直接お問い合わせください。
