クローズアップ
一般社団法人 技能実習生生活支援機構(TITL / Organization for Technical Intern Trainee Life support) ~日本で暮らす外国人技能実習生たちの笑顔のために生活をサポート~

外国人技能実習生の限られた滞在期間中、日本での生活をもっと豊かなものにしたいと、生活支援活動を行っているのが、江戸川区にある一般社団法人 技能実習生生活支援機構(Organization for Technical Intern Trainee Life support /以後、TITL<ティトル>)です。技術の習得に向けて日夜仕事に励む若者たち。しかし、彼らの日本での「生活」は、あまり楽しいものとはいえない現状も聞こえてきます。そんな技能実習生たちの生活をサポートする団体TITLの代表理事である川手尚哉さん、理事の鈴木徳光さんのお二人にお話を伺いました。
来日する若い技能実習生たちの現実を初めて知る
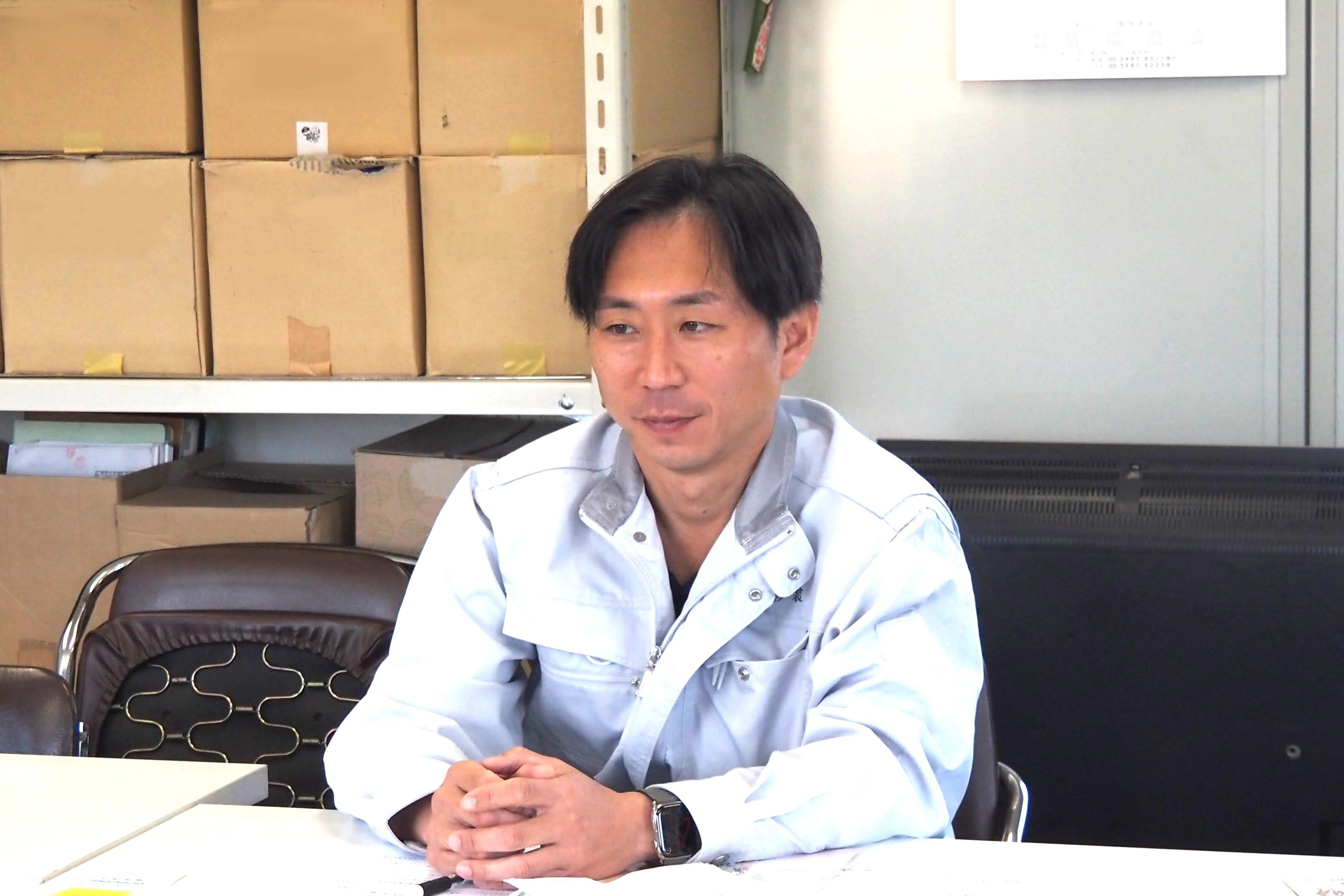
1993年に導入された技能実習制度は、外国人が日本に在留し報酬を伴う技能実習が受けられる制度です。 日本に滞在する外国人技能実習生は2021年6月末で35万4,104人(出入国在留管理庁調べ)、人手不足が深刻な建設業などをはじめ、幅広い業種・職種で受け入れが進んでいます。建築関係の会社を営む川手尚哉さんがその存在を知ったのは、会社で初めて技能実習生を雇用することになった2016年の8月でした。
「それまでは『技能実習』という制度すら知りませんでした。興味を持って、いろいろと調べたんです」。ネットなどで調べるうちに、川手さんはある実習修了生の論文に目を留めます。
「その論文によると、高い技術が学べるなど、入国前は日本に対して良いイメージを持っている人が90%以上。ところが実際来てみたら、孤独や孤立感、考えていたような仕事内容ではなかったなど、最終的にかなり多くの実習生が悪いイメージを持って帰国するという内容でした。せっかく日本に来てくれるなら、その期間を楽しい思い出にしてほしいと思ったんです」。
同業者や異業種の知人、地元の友人などと話をするなかで、こうした現状を変えられないかと、大学の先輩後輩で地元も同じだった川手さん、鈴木さんともう一人の鈴木さんの3人で団体設立を考えるようになったといいます。
職場でのコミュニケーションの問題を解決するため、日本語教室から活動をスタート

川手さんたちは、2017年12月18日にTITLを設立します。
「実習生の生活をサポートできる、実習生が集まるプラットフォームのような組織になれないか、と団体を設立したんですが、会社に来た実習生を見て、まず言葉の問題が大きいと思いました。言葉が通じないから、日本人ワーカーとコミュニケーションが取れない。日本人も実習生も、お互いにイライラしたストレスのある状態になってしまいます」と、川手さん。
実習生たちは来日前・来日後の研修などで日本語を勉強する機会はありますが、人によってレベルが異なります。基本的には「日本語能力試験(JLPT)」のN4~N5(初級)レベルで来日する実習生が多いといわれますが、日常的なやり取りを理解するにはその上のN3レベルが必要とされるため、職場などでのコミュニケーションに不安を抱えている実習生は多いといいます。ー「日本語能力試験N1~N5:認定の目安」
そこで、TITLの活動は日本語教室からスタートさせたそうです。
実習生の日本での生活を広げる出会いの場に

日本語教室を始める際はまず、月2回、江戸川区の建設業関係の企業が加盟する協会で会議室を借り、各社で雇用している実習生を20~30人ほど集めました。ところが、1年経つころにコロナ禍で状況が一変、教室はオンライン開催となりました。オンラインになったことで会場設営の手間がなくなり、開催の頻度が高まったといいます。現在は要望があれば毎日のように教室を開催しています。さらに実習生同士の繋がりで都外の岐阜や愛知、茨城、青森などからも実習生が参加したり、帰国後に本国から参加している元実習生もいるそうです。
来日直後の実習生は、実習先や近所に友人も知り合いもいないことが多く、ホームシックや孤独感を感じやすいといいます。しかし、日本語教室などの活動のなかで実習生同士友だちになったり、近所の日本人と知り合ったりするなど、TITLが実習生の生活を広げる出会いの場になっているといいます。また、地域のお祭りや季節のイベントへの参加を通して日本文化を体験する機会も提供しています。
お祭りやイベントがコロナ禍で中断するなか、癒しになった「多文化共生農園」

日本語教室はオンラインで継続したものの、コロナ禍により、お花見や餅つき、お祭りなど実習生が楽しんでいた多くのイベントが中止になりました。そこで2021年4月、TITLは借りた農地を「多文化共生農園」と名付け、野菜などの栽培を始めます。
「寮の屋上で植物を育てたいと実習生の一人が言ってきて、そこで思いついたんです」と、会社の近くに農地を借りた鈴木さんは言います。
「実習生の中には農村の出身者も多く、喜んで参加してくれます。野菜を買うお金の節約になりますし、土をいじることで安らぎの時間にもなっているようです。野菜だけでなく敷地内の梅の実でジャムを作ったり、レモングラスも植えました。実習生たちの知恵を借りながら野菜を無農薬で育てる試みもしています」。
多くの実習生の母国料理に用いられるレモングラスは日本で購入すると高価なため、実習生たちからとても好評だそうです。この農地では実習生をはじめ、地元のボランティアや近所の子どもたち、PBL(課題解決型学習-Project Based Learning)授業の一環として和洋女子大学国際学科の学生も参加し、みんなで管理しています。
「実習生の母国の料理など、収穫した食材で文化交流も今後していけたら」と鈴木さんは話します。
ただの「労働力」ではなく、日本で一緒に働く「仲間」だから

TITLがこれまでに関わった技能実習生は3か国(ベトナム、ミャンマー、インドネシア)およそ100人以上。この先の活動については現在模索中だそうです。
「団体設立から3年経って、今ちょうど次にどう進もうか考えて模索しているところなんです。ボランティアの方にも協力してもらっていますが、基本の運営は立ち上げメンバーを中心に4、5名で行っており、(私たちの)本業は別にあるので、TITLの活動とのバランスが難しいなと思っています」と鈴木さん。
「日本語教室に参加した技能実習生の中には、お礼を言ってくれる人、何かあれば我々を助けると言ってくれる人、実習終了後も参加してくれる人もいます。やればやるほど忙しくはなりますが、団体としての活動は維持していきたいと思っています」と川手さん。
TITLは許認可を受け、特定技能の登録支援機関や無料職業紹介所として、実習生の生活だけでなく、働く環境のサポートも行っています。
人材不足の救世主として職場に迎えた、「技能実習生」。ただの「労働力」としてではなくまずは一人の「人」として、限られた日本滞在期間の生活がより豊かなものになるようTITLの皆さんはその笑顔を守ろうとしています。
*本記事は取材時点での情報をもとに作成しています。最新の情報については、団体へ直接お問い合わせください。
