クローズアップ
NPO法人 ASIAN COMMUNITY TAKASHIMADAIRA(高島平ACT) 〜 外国籍住民と高齢者住民双方のパワーを活かして、互いに住みやすい街に 〜

板橋区にある高島平団地は1970年代に造られた大規模団地として広く知られています。その高島平団地の中で活動しているのが、NPO法人ASIAN COMMUNITY TAKASHIMADAIRA(以下、高島平ACT)です。外国籍住民と日本人住民が共生、共働しながら、一緒に街づくりを行っていくことを目指しています。
日本語教室をはじめ、多文化理解のための連続講座、過去にはコミュニティ・スペースの設置など、多種多彩なイベントを積極的に展開。外国籍の住民も理事に就任するなど主体的に参加しています。そんな高島平ACTの理事、吉成勝男さんをはじめ、日本語教室ボランティアの原田和子さんと見目清子さん、中国語教室でボランティア大学院生の陳暁鋒さんにお話をうかがいました。
かつての東洋一のマンモス団地に急増する外国籍住民

板橋区高島平2丁目、3丁目に広がる高島平団地は1972年に入居がスタートしました。当時、日本にはまだあまりなかった11〜14階建ての高層住宅が立ち並び、日本の住宅の近代化を強く印象づけてきました。それから50年が経過した現在も、賃貸住宅が8,287戸、分譲住宅は1,883 戸と総戸数1万を超える規模を誇っています。かつては「東洋一のマンモス団地」といわれたこの団地でここ数年急速に進んでいるのが外国籍住民の増加による“多文化”化だといいます。2011年12月に設立された高島平ACTは、高島平団地在住の外国籍の住民と日本人住民が交流をしながら、相互理解や双方が住みやすい街づくりを目指して活動してきました。団体設立の翌年にはNPO法人格を取得し、フィリピン系ルーツを持つ住民が理事になるなど、外国人も活動に積極的に参加してきました。また、ここ1〜2年は中国人が急増しており、現在中国の方も監事として参加しています。自治会とも連携し、自治会がこれまであまり踏み込めなかった外国籍住民についての問題解決のための橋渡し役となってきました。
「地域で外国籍住民と対立するのではなく、地域コミュニティの中に外国人も入ってもらい、一緒に地域を作っていく、それが地域の結束性にも繋がると思うんです」と吉成さん。
交流と相互理解を通じ、同じ地域に暮らす仲間としての結束を

外国籍住民と日本人住民とで実際に大きなトラブルがあったわけではないものの、外国籍住民が増える中で、トラブルに発展しそうな声は少しずつ聞くようになったといいます。「例えば、ごみ捨て場に粗大ごみが捨てられていたら、『これは外国人が捨てたに違いない』という人がいたり。実際に見たわけじゃなくても、『こういうことをするのは外国人に決まっている』と。あまり関わったことのない外国籍住民にたいして無意識にそうした偏見や差別的な感情を持ってしまっている人もいます。ただ、その辺りは実際に話して、交流して理解し合えれば、解決できると思うんです」と吉成さんは話します。住民同士の相互理解のために開催する多文化講座のテーマは、外国籍住民を守る法律から防災、難民問題まで多岐に渡ります。講座や交流イベントへの住民の参加は増えているといい、「未知な人たちに対する不安がある一方で、その不安を解消するために『知りたい』という好奇心のようなものも強いように感じます。『多文化』や『外国人』への関心は高くても、自分がどう関わっていいのかわからない、と感じている人も多いので、そのような人たちに機会を提供できたらいいなと思います」。
外国籍住民と高齢住民、それぞれの力を活用した地域づくり

外国籍住民に特化し支援をしていこうと始めた団体の活動でしたが、地域で活動するなかでボランティアや講座に参加してくれた高齢住民との関係が少しずつできていったといいます。そうした中、現在板橋区の中でももっとも進んでいるという、この地域の高齢化の問題もNPOとして無視できないものとなりました。そこから、“多文化”化と高齢化、2つの地域の特性を活かした活動を模索していきました。「高齢住民と外国籍住民とで、お互いの持つ力を活用することで相互作用の生まれる活動ができないか、と考えたんです」と吉成さん。外国籍住民が日本で暮らすために必要な日本語教室の講師に経験と知識が豊富な高齢住民を、高齢住民の世界を広げる外国語講座やスマホ講座の講師に外国籍住民を、とお互いに助け合い学び合う場と機会を創出してきました。
日本語教室ボランティアの原田さんは「(教室参加者は)中国の方が多いのですが、すらすら読めても、自分の言葉で話せない人が多い。ここが彼らにとっての日本での経験の場として手助けができるのかなと思っています」と話します。教室では日本語学校のように点数で評価はせず、参加者に合わせたペースや教え方で勉強し、それが日常の交流にもつながっているといいます。
お互いに交流を望む外国籍住民と日本人住民をつなぐ
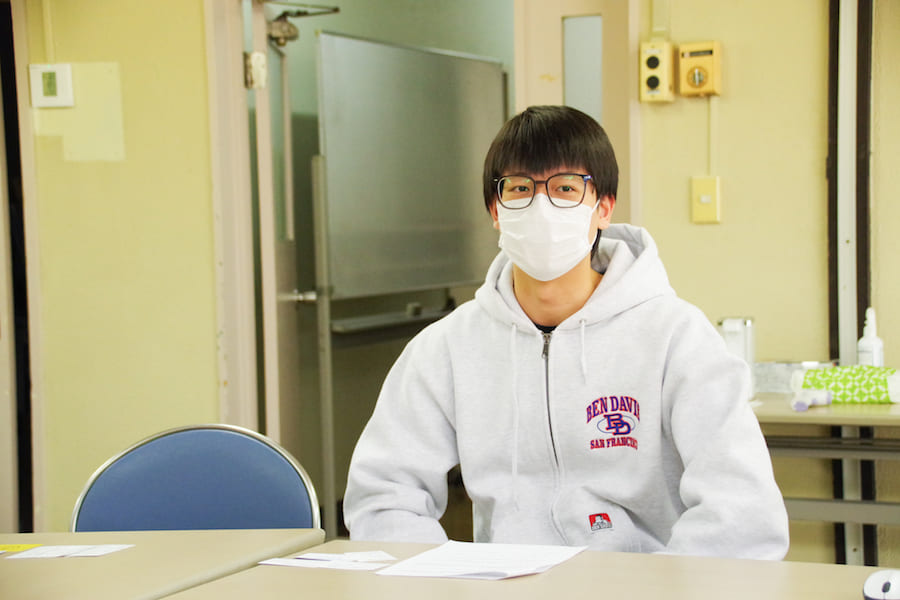
「以前も日本に住んでいたことはありましたが、ここに住んで高島平ACTに参加して、こういった日本での住民の活動を初めて経験しました。勉強になることが多いです。(地域の人たちと)もっと交流したいです」と話すのは、中国語教室のボランティア講師を担当する、中国出身の大学院生の陳さん。中国人住民の多いこの地域で、日本人に中国語を通し中国の文化も伝えています。陳さんのように日本人住民との交流や付き合いに意欲的な姿勢を見せる外国籍住民は多く、以前、区が行った調査でも9割以上がそうした意向を見せました。また、日本語教室ボランティアの見目さんも、「吉成さんから声をかけられて、コンセプトに共感を持ったので参加しました。いろいろな国の人とつながっていく、また地域とつながりを持つということは大事だと思いましたね」と話します。
2014年から2017年にかけては、外国籍住民や高齢住民が集い交流できるコミュニティ・スペース「ハロハロ・グルメ」をオープンしました。そこでは日本語・英語・タガログ語の教室、認知症カフェ、ランチクラブ、お坊さんダイニング、バングラデシュの民族バンドによるライブなど多種多様な活動が行われました。閉店後もこうした活動は集会所等を利用して続けられています。
高島平ACTの活動が提示する、これからの街づくり

「私自身、この団体で活動を始めるまでは近隣関係もほとんどなく、隣の人にも会ったことがなかったんです」と話す吉成さん。この地域の自治会立ち上げ時からこの団地に50年以上住んでいる原田さんや見目さんも「若い人たちがただでさえ減っているなか、自治会活動に目を向ける人が少ないんです」と声を揃えます。かつて自治会を組織し地域活動を盛り上げた世代が高齢化し、引っ越しなど住民の入れ替わりで近隣関係が希薄化する現状に、外国籍住民との共生・共働という新たな解決策を提示する高島平ACTの活動。今後は外国にルーツを持つ子どもたちへの母語・文化教育などさらに活動の幅を広げていきたいといいます。これからの目標を伺うと、「講座を聞いた人たちがボランティアに参加したくなるような工夫をしていきたいです。地域コミュニティの人間関係などが壊れてきているなかで、ボランティアさんたちと一緒に助け合いながら地域づくりというところでの活動をやっていきたいです」と吉成さん。
高島平ACTの取り組みが、これからの街づくりを大きく変えていくかもしれません。
*本記事は取材時点での情報をもとに作成しています。最新の情報については、団体へ直接お問い合わせください。
