クローズアップ
公益社団法人 シャンティ国際ボランティア会 ~ 海外の支援活動で培った経験を日本国内の活動に生かして ~

シャンティ国際ボランティア会(シャンティ)は、カンボジア難民の緊急人道支援救援活動に携わった曹洞宗東南アジア難民救済会議(JSRC)のボランティア有志によって、1981年に設立されました。日本にまだ、NGOが数団体しかなかったころのことです。以来、アジアの国々で教育文化支援活動を展開し続け、本年、団体設立40周年を迎えました。今回は、新たな国内事業として取り組んでいる外国ルーツの子どもや在住外国人を支援する活動について、地球市民事業課課長の市川斉さんと地球市民事業課で国内事業を担当する村松清玄さんにお話をうかがいました。
子どもたちが安心して学べる環境をつくるために
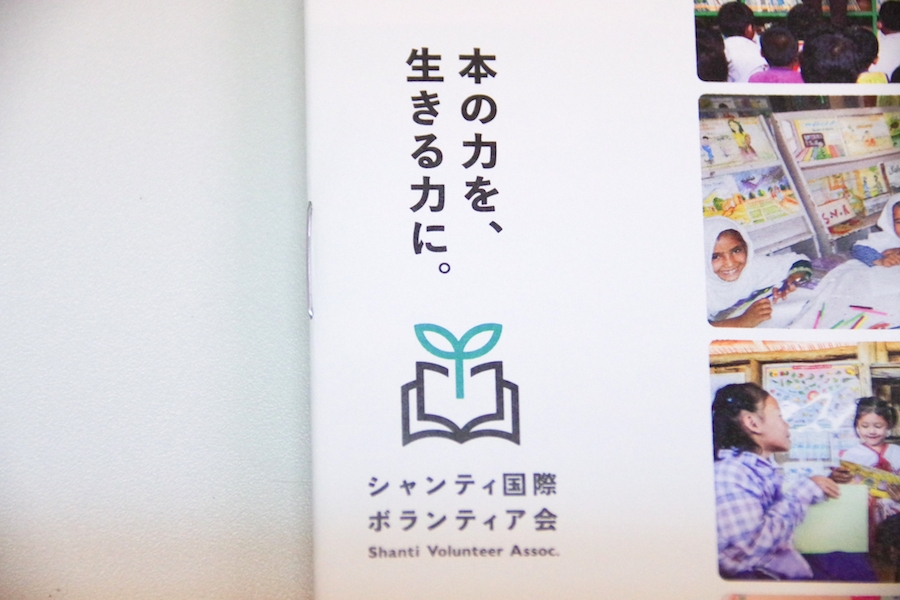
シャンティは40年にわたり、アジアの子どもたちへの教育支援活動を続けてきました。「教育には人生を変える力がある」と信じ、紛争や貧困、自然災害といった厳しい環境下でも安心して学べるよう、図書館活動や学校建設、人材育成などを行っています。1980年にタイに最初の海外事務所を開設して以来、活動地域は7か国8地域に広がりました。2020年末までに子どもたちに届けた絵本は約34万冊、「学びを届ける人」を育成する研修への参加者は3万8千人以上に上ります。そして安心して学べる場として建設した学校は400校を超え、設置した図書館・図書室の数もおよそ1000館・室に。さらに国内外で実施した緊急人道支援も通算76回を数えます。
日本は経済先進国から課題先進国に

海外で実績と経験を積んだシャンティが、新たな国内事業を展開し始めたと聞き、市川さんにその理由を伺いました。「1980~90年代の初めごろ、日本は豊かで9割が中間層といわれていました。しかしそれから30年が過ぎ、経済がグローバル化したことで、一部の富裕層と大多数の貧困層に二極化するという現象が日本を含めて世界中で起きています。経済先進国だった日本が課題先進国となり、貧困や教育の格差が顕著になってきたため、日本のNGOがここ数年で海外だけでなく国内での支援活動へとシフトしています。私たちも5年ほど前から検討を始め、ようやく形になったのが、外国ルーツの子どもたちを対象とした支援事業でした」。
2020年、シャンティの新たな国内事業として、NPO法人 豊島子どもWAKUWAKUネットワークとの協動で、外国ルーツの子どもたちの居場所づくりがスタートしました。
外国ルーツの子どもたちの居場所づくり

当初予定していた対面での活動がコロナ禍で難しくなったため、居場所づくりはオンラインで行われることとなりました。毎週土曜日の18時~20時まで、Zoomを利用して「オンライン居場所」を実施しています。参加するのは小学校の高学年から高校生相当までの子どもたちで、毎回10人前後が集まるそうです。
「オンライン居場所」ではまず、「話したくないときは、話さないで」「ほかのひとを大切にしよう」など『大切なこと』が書かれたスライドを見た後、ミニゲームやクイズで場をほぐします。それから、その日のテーマについて、みんなで考えます。「権利ってなに?」「各国のお正月」「他者や社会について考える」など、取り上げるテーマは多岐にわたります。
「『外国ルーツの子どもたち』と一括りにしがちですが、国籍も環境も宗教も、在留資格から経済的な事情まで一人ひとり違います。外国ルーツの子どもにも多様性があることに気づかされました」と話してくれたのは、事業を担当している村松さんです。豊島区の池袋周辺には外国ルーツの子どもが大勢いますが、それでもマイノリティとして暮らすことのストレスや心の孤立といった問題あると言われています。「オンライン居場所」では年齢もルーツも違う子どもたちが一緒に楽しい時間を過ごします。また、個人的に話したいことがあれば、ブレイクアウトルームで対応します。「参加する子どもたちは、ここを居場所だと感じてくれていると思います」と村松さん。「だからこそ毎週来てくれるのだと思います」。
相談会と食料配布をセットで行う豊島区のフードパントリー

また、シャンティでは、東京パブリック法律事務所、豊島区民社会福祉協議会と連携し、コロナ禍で困窮する外国人への緊急生活支援の一環として、豊島区各地でフードパントリーと相談会をはじめとする包括支援を実施しています。
「豊島区は日本の市区町村別では、8番目に多く外国人が住んでいます。豊島区民社会福祉協議会がコロナ禍の特例貸付をしたところ、1万6千件の申し込みがあり、その半数が外国人だったそうです。豊島区に住む外国人の約半数は中国の出身者ですが、特例貸付の申請者の8割がネパールとミャンマーの出身者だということがわかっています」と市川さん。
「フードパントリーの情報は、豊島社協さんから会場の周辺地区に住んでいる外国人の方を中心に案内してもらっていますが、最近はFacebookの告知を見て遠方からいらっしゃる方もいます。食料配布も大切ですが、困り事の相談の場を提供することがより大きな目的です」と村松さん。「弁護士と社会福祉協議会のソーシャルワーカーと、ネパール語、ミャンマー語、英語・中国語に対応できるコーディネーターを配置して、できるだけ母語で相談できるようにしています。相談内容は、仕事や経済的な問題と在留資格の問題が非常に多いです」。休眠預金を活用して実施しているこのフードパントリーと相談会は、月1~2回のペースで開催されています。これまでに8回開かれ(2021年11月現在)、277名が参加したそうです。継続的な支援が必要とされた方には、コーディネーターや弁護士、ソーシャルワーカーによる個別支援を行っています。
海外で培った経験をコーディネーションで生かす

シャンティの在留外国人支援事業はまだ始まったばかりです。30年以上にわたってシャンティの活動に携わり、難民キャンプや紛争下のアフガニスタンなどでさまざまな経験を積んできた市川さんはこういいます。「厳しい環境にいる人に寄り添うことや居場所をつくることはとても大切です。在留外国人支援に関しては、シャンティはまだ修行中です。でも、海外での活動経験をもとに、問題の解決に向け、さまざまなステークホルダーをつなげ、コーディネーションするという形で貢献できるのではないかと思っています」。
また、国内事業を担当する村松さんはこう話してくれました。「外国ルーツの子どもの居場所づくりを中心になって担っているのは、大学院生のスタッフたちです。ネパールと中国にルーツを持つ大学生も通訳として活躍しています。お正月以外は毎週末、欠かさず「オンライン居場所」を開催する彼らの姿を見ていると、本当に子どもたちのことを考えていることが伝わってきて感心します。教えられることも多いです。「オンライン居場所」は、すでに70回以上(2021年11月現在)行われています。コロナが収束すれば、対面での居場所づくりに取り組みたいです。子どもたちの居場所のひとつとして、ずっと続けていければと思っています」。
シャンティが国内で始めた2つの在留外国人支援事業が、今後どんな広がりを見せるのか楽しみです。
*本記事は取材時点での情報をもとに作成しています。最新の情報については、団体へ直接お問い合わせください。
