クローズアップ
NPO法人 グロウバル言語文化研究会 ~世界に通じるコミュニケーション力を持った子どもたちを育む~

多摩市内の公民館にて。代表の中村祐子さんを挟んで、理事の大槻友紀さん(左)と服部千鶴さん(右)。
*この記事は、東京都国際交流委員会が運営していたウェブサイトに掲載したものです。
今月のクローズアップは、NPO法人 グロウバル言語文化研究会のご紹介です。グロウバル言語文化研究会(以下、グロウバル)では、子どもたちが異なる言語や文化に触れ、さまざまな国の人たちと交流する機会を提供しています。グロウバルのクラス活動や国際交流イベントで外国人と触れ合う体験を重ねた子どもたちは、世界に視野を広げ、それぞれが目指す道へと進んでいくそうです。1987年の設立以降、時代の移り変わりに柔軟に対応しながら、「真の国際交流の担い手」の育成に取り組み続けてきたグロウバル。その活動の詳細について、代表の中村祐子さんと理事の服部千鶴さん、大槻友紀さんに伺いました。
![]() グロウバル言語文化研究会の設立の経緯を教えてください。
グロウバル言語文化研究会の設立の経緯を教えてください。
 中村さん
中村さん
グロウバル言語文化研究会は、子どもたちのための外国語活動や国際交流を進め、国際感覚豊かで自立した青少年を育成することを目的として、1987年10月に設立されました。当時はまだ外国人が珍しく、普通に会って交流することが難しい時代でしたから、地域に住む外国人をクラスに招いたり、国際交流キャンプを実施したりといったグロウバルの取組みは、とてもユニークなものだったと思います。当初は、複数の言語を同時に習得することを目指しており、英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、韓国語、中国語などを子どもたちがシャワーのように浴びて身につけられるよう、多言語のオリジナル教材の作成も行っていました。2000年にNPO法人となり、現在は東京都多摩市に事務所を置いて活動しています。


毎年開催している国際交流キャンプ。
自然の中でさまざまな国の言葉や文化を学び、友情を育みます。
© グロウバル言語文化研究会
![]() 現在のおもな活動内容を教えてください。
現在のおもな活動内容を教えてください。

 中村さん
中村さん
ひとつは言語の習得を目指すクラス活動です。年代別に英語学習のクラスがあり、音やリズムで楽しく英語を学ぶところから、自分の意見を英語で表現するところまでステップアップしていきます。現在は実際のニーズも踏まえ、英語の習得を中心としていますが、その他の言語に触れる活動も行っています。世界中の人たちと交流することが私たちの目標ですから、いろいろな国のあいさつや自己紹介の言葉を身につけてくれたら嬉しいですね。

 服部さん
服部さん
定期的に外国人を呼んでいるクラスもあります。招いているのは、主に中央大学や東京学芸大学の留学生で国籍はさまざまです。彼らに母国語でのあいさつやその国のことを教えてもらい、代わりに子どもたちが日本の遊びを教えます。子どもたちには国際交流を体験する機会を、留学生には生の日本語に触れるチャンスを提供する形となっており、とてもいい相互作用が生まれていると思います。将来ALT(外国語指導助手)として活動することを希望している留学生にとっては、言葉や文化を教える経験を積む貴重な機会にもなっているようです。
![]() 外国人を交えたクラス活動で、何か変わった試みをされることはありますか。
外国人を交えたクラス活動で、何か変わった試みをされることはありますか。

 大槻さん
大槻さん
ときどき料理などもしますね。例えば、私たちの考えるサンドイッチと外国人の考えるサンドイッチ、中身がまったく違うということを一緒に作りながら体験してみたことがあります。また、遠くエジプトからやって来た留学生とエジプト料理を作ってみたら、ほとんどの食材が日本人になじみのあるものだったことに驚かされたこともありました。一方の留学生の方もいろいろと面白い体験ができているのではないでしょうか。動物園に出かけたとき、留学生にもお弁当も作ってあげたのですが、家庭で作ったお弁当を食べるのが初めてだったらしく、のぞき込むようにおにぎりの具を確認していた姿が印象に残っています。「帰国したら親に作ってあげたいからレシピを教えて欲しい」と頼まれたりもしました。
![]() クラス活動以外には、どのような活動をされているのでしょうか。
クラス活動以外には、どのような活動をされているのでしょうか。
 中村さん
中村さん
一年を通してさまざまな国際交流イベントを展開しています。グロウバルを代表する活動の1つである国際交流キャンプは、日帰りで実施することもあれば、1泊、2泊と宿泊を伴うことも。さまざまな年齢の子どもたちが参加する中で、中学生以上はリーダーとしてそれぞれの役割を与えられ、キャンプの運営を担います。ところが残念なことに、この頃の中学生・高校生・大学生は、部活や塾、サークル活動など忙しく、リーダーを務める年代のキャンプへの参加率が下がってきてしまいました。そこで近年はリーダーを育成してキャンプを運営していく方針から、この地域の留学生にスタッフとして参加してもらうやり方へと切り替えています。グロウバルではこのほかにも、中野区内の幼稚園での国際理解クラス、日野市の公立小学校でのALT、多摩市国際交流センターでの「夏休み英語ひろば」などを担当、さらにホームステイ交流なども行っています。
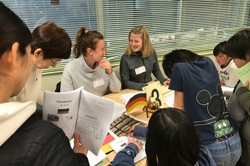

オーストラリア、ロシア、アメリカ、メキシコ、ドイツ、ガボン、マラウィ、中国の留学生や在日外国人の方々との国際交流デー。
それぞれの国の今を紹介してもらいました。
© グロウバル言語文化研究会
![]() グロウバルの活動の特色は、どんなところにあるのでしょうか。
グロウバルの活動の特色は、どんなところにあるのでしょうか。
 中村さん
中村さん
「体験すること」を重視しているのが大きな特色です。外国人と直接触れ合いさまざまな体験をすることに重きを置いて運営してきたことが、国際交流の機会を提供する団体がこれだけ増えた現在も活動が継続できている要因ではないでしょうか。グロウバルでは、より多くの体験型の国際交流の機会を子どもたちに提供できるよう、他団体との連携にも力を入れており、その代表的なものが市民団体「ワールドキャンパス多摩(WCT)」との協働です。ワールドキャンパスとは、世界各国からやって来た若者たちが日本各地でホームステイしながら交流・学習するプログラムで、WCTは彼らが多摩市に滞在する1週間、さまざまな交流活動を行います。グロウバルの高校生・大学生も毎年この企画にボランティアとして参加しており、イベントの進行やサポート、東京観光の案内役を務めるなど、貴重な体験をさせてもらっているのです。さらに、ワールドキャンパスがきっかけで知り合ったスウェーデンのカルマルインターナショナルハイスクールの日本人の先生と連携し、お互いの生徒が行き来する交流も始まりました。


世界の若者たちが多摩市を訪れる「World Campus in 多摩」では、
学生たちがボランティアとして活躍します。
© グロウバル言語文化研究会
![]() グロウバルの活動に参加した子どもたちには、どのような変化が見られますか。
グロウバルの活動に参加した子どもたちには、どのような変化が見られますか。
 大槻さん
大槻さん
国際交流キャンプにスタッフとして参加した留学生にお国紹介をしてもらうと、まるで自国の大使であるかのような見事なプレゼンを披露してくれます。彼らとわずかしか年の違わないグロウバルの高校生・大学生はその姿を見て衝撃を受けると同時に、自分がそもそも日本のことをよく知らないことに気づくようです。グロウバルの活動は、異なる文化や価値観に触れるだけでなく、自身のアイデンティティについて考える機会にもなっているように思います。
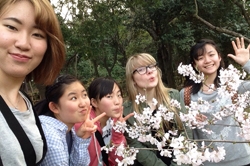

スウェーデンの高校生のホームステイ受入れ。
ホームステイは将来の国際的人材育成に役立ちます。
© グロウバル言語文化研究会
 中村さん
中村さん
WCTで大学生に混じって東京案内に参加したある高校生の話です。周りの大学生が楽しげに外国人とおしゃべりをしているのに、彼女は頭が真っ白になって英語がまったく出てこない。伝えたいことがたくさんあるのにもどかしく悔しい思いをした彼女は、その後一生懸命勉強し、大学生になると海外留学へと旅立ちました。最近の若い人は内向きで日本から出たがらないと言われますが、グロウバルの子どもたちには海外へ行くことを希望し、実際に行動に移す子どもが少なくありません。グロウバルでのさまざまな体験を通して自分が何をしたいかを考え、羽ばたいていく子どもが多いことはとても嬉しいことです。グロウバルは小さな団体ですが、今後も他団体とうまく連携しながら、活動を継続・発展させていきたいと考えています。
