クローズアップ
社会福祉法人 国際視覚障害者援護協会 ~発展途上国の視覚障害者の自立を日本留学でサポートする~

社会福祉法人国際視覚障害者援護協会
理事長 石渡 博明さん(右)
理事 新井 愛一郎さん(左)
*この記事は、東京都国際交流委員会が運営していたウェブサイトに掲載したものです。
今月のクローズアップでは、社会福祉法人 国際視覚障害者援護協会(IAVI)をご紹介します。経済的自立を目指す視覚障害者にとって大きな強みとなるのが、三療と呼ばれる「あんま・鍼・灸」の知識と技術です。IAVIでは、アジア・アフリカなどの発展途上国から視覚に障害を持った若者を招き、日本で三療やIT技術などを学ぶ機会を提供しています。IAVIの奨学制度で来日した留学生には、帰国後に母国の視覚障害者福祉に貢献することも求められます。今回は、海外からやってきた視覚障害者をどのようにサポートしているのか、理事長の石渡博明さんと理事の新井愛一郎さんに詳しくお話をうかがいました。
![]() IAVI設立の経緯を教えてください。
IAVI設立の経緯を教えてください。
 石渡さん
石渡さん
IAVIの前身となる「国際盲人クラブ(ICB)」が発足したのは、1971年のことです。韓国、台湾、香港から日本に留学していた4人の視覚障害者が出会い、自分たちだけが日本留学というチャンスに恵まれるのは申し訳ない、ほかのアジアの視覚障害者にも門戸を広げたいと考え、韓国の方がこの団体を設立したのです。1976年に初めての援助活動として韓国からの自費留学生を支援、1981年には奨学制度を創設し、その翌年からほぼ毎年留学生を受け入れるようになりました。その後、1995年に社会福祉法人国際視覚障害者援護協会(IAVI)となり、これまでにアジア、アフリカなどの19カ国から約80名の視覚障害者を日本に招いてきました。この実績が認められ、2000年からは、事前研修の経費の一部に文部科学省の補助金をいただいています。
![]() IAVIの主な事業内容について教えてください。
IAVIの主な事業内容について教えてください。
 石渡さん
石渡さん
奨学制度で来日する留学生の募集から帰国後のフォローまでを主要な事業として行っています。IAVIの奨学制度は、教育環境や就労機会に恵まれない国々の若い視覚障害者に日本で学ぶ機会を提供し、経済的自立を可能にする三療の知識・技術やコンピュータを活用したIT技術などを習得してもらうことを目的としています。留学生たちには、帰国後に母国の障害者福祉を向上させていくリーダーとなれるよう、日本の視覚障害者の状況や福祉政策を学ぶことも求められます。現在はキルギス、ミャンマー、ベトナム、インドネシアからの留学生が日本の盲学校等で勉強中です。留学生は基本的に年に二人。9月末から10月初めに来日し、事務所兼研修所の舟橋記念会館に泊まり込んで、約半年間、日本語、日本点字、歩行訓練、生活訓練などの研修を受けつつ、留学先の盲学校を決めます。そして翌年4月から3年間、盲学校の高等部・専攻科で三療を習得。卒業と併せて、国家資格を取得して帰国することを目指します。

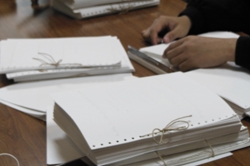
舟橋記念会館での日本点字の研修と分厚い点字教材。
留学生たちは盲学校に入学後も、長期休暇になるとこの会館に帰ってきます。
![]() 留学生たちの母国では、視覚障害者の教育や就労の機会があまりないのでしょうか。
留学生たちの母国では、視覚障害者の教育や就労の機会があまりないのでしょうか。

新井さん
日本では、あんま・鍼・灸が視覚障害者の大切な仕事として定着しており、盲学校で3年間学んで三療の資格を取得すればそれを仕事につなげることができます。ところが、アジアをはじめとする発展途上国ではこうしたシステムが整っていないため、仕事で自立していくことが難しく、社会的評価も低いままというのが現状です。
石渡さん
また、日本では国立の筑波大学附属視覚特別支援学校のほか、自治体ごとに盲学校あるいは特別支援学校が最低1校はありますが、途上国では盲学校が全国に1校というところも少なくありません。さらに国によっては、その盲学校さえ点字教室にすぎないこともあり、そうした厳しい状況だからこそ、多くの人が日本で学ぶことを希望するのです。留学生たちは、日本語と日本語点字を覚え、盲学校の受験に備え、入学後は国家試験に向けて勉強に励みます。せっかく来日したのだからいろいろな経験をしてほしいと私たちも思うのですが、ひたすら勉強だけの日々になってしまい可哀想なくらいです。
![]() 帰国した留学生たちは、どのような形で活躍しているのでしょうか。
帰国した留学生たちは、どのような形で活躍しているのでしょうか。

石渡さん
日本で習得した三療技術をもとに治療院を開設したり、障害者関連施設に勤務するといった形で自立と社会参加を果たすとともに、後進の指導に務めたり、日本での体験を広めたりと、視覚障害者福祉の向上に大きな役割を果たしてくれています。
新井さん
帰国した留学生たちは、日本からやって来る視覚障害者の施設見学に同行、通訳を務めるなどの活動もしてくれています。日本との交流、とりわけ視覚障害者同士の交流の担い手になってくれる彼らは、私たちの宝です。また、日本での体験を生きた情報として母国に提供できるというのも素晴らしいことだと思います。たとえば、あるマレーシアの留学生が日本の点字ブロックや点字と音声付きの券売機などを撮影しユーチューブで流したところ、大きな反響があったそうです。日本では視覚障害者がひとりで電車に乗り、各駅で駅員のサポートを受けながら目的地にたどり着くことができる。そういった情報を持ち帰り知らせることが、その国の視覚障害者の自立に向けた環境整備に役立つのです。


舟橋記念会館に並ぶ点字辞書。一冊の国語辞典が棚一杯の点字辞書となります。(左)
スタッフの庄さんが点字印刷機を実演してくださいました。(右)
![]() 活動において、課題となっているのはどんなことでしょうか。
活動において、課題となっているのはどんなことでしょうか。


石渡さん
日本で勉強したいと私たちにコンタクトを取ってくる人の数は増えているのにも関わらず、文部科学省から支給される補助金はほぼ毎年減り続け、予算不足は深刻です。私たちが綱渡りのような状態で留学生の受入れを行うのではなく、日本の視覚障害者、視覚障害者を支援する団体と関係者が一体になって、留学生の受入れに取り組んでいくようになることを願っています。

新井さん
日本は、国として何十万人もの外国人留学生の受入れを目指すと言いながら、そこに視覚障害者の留学生が含まれていないのは残念なことです。海外の視覚障害者は日本とのつながりを強く求めているのだから、それに応える体制を整えるべきだと思います。
![]() 今後、取り組みたいことなどをお聞かせください。
今後、取り組みたいことなどをお聞かせください。

石渡さん
留学生の出身国を紹介する冊子づくりを続けたいと思っています。今年3月に『白い杖の留学生 キルギス編』を発行したのですが、モンゴル編、ミャンマー編、ベトナム編なども作成していきたいです。その国の視覚障害者事情の紹介も含めた冊子にできればと考えています。また、帰国した元留学生たちが日本で一堂に会し、情報交換をしつつ、互いを励まし合う機会が作れたらと思っています。
新井さん
留学生同士の横のつながりが深まることによって、互いがより発展するきっかけになればうれしいですし、日本もいろいろと変わってきていますから、ぜひ今の日本も体験してもらいたいです。きっとその中から、「うちの国でもこういうことができれば」という新たなアイデアも生まれてくるでしょう。SNSが発達し、直接会わなくてもコミュニケーションを取れる時代になりましたが、一度日本で集合したいものです。
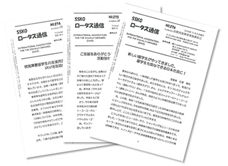

定期的に発行している「ロータス通信」と「白い杖の留学生 キルギス編」
![]() 視覚障害者の転落事故が相次いでいますが、どのような思いを抱かれますか。
視覚障害者の転落事故が相次いでいますが、どのような思いを抱かれますか。

石渡さん
日本は「障害者にやさしい国」であると期待してやって来る留学生たちを裏切ってはいけないと感じます。ハードの面でも、ソフトの面でも、人々の心がもっと開かれて、障害がある人もない人もお互いに助け合って暮らせる社会を実現したいですね。
新井さん
世界には、視覚障害者が一人で自立していろいろなところに行くということがなかなか叶わない国もあります。日本はそれが可能なところが素晴らしいと留学生たちも感じるようです。だからこそ私たち日本人は、障害者が本当の意味で自立して生活できるような社会を作って、彼らにもっともっといいものを見せてあげなければと思います。
