クローズアップ
特定非営利活動法人 CWS JAPAN ~国内外のネットワークを活かして、災害に負けない社会づくりを~

CWS JAPAN
事務局長 小美野剛さん
*この記事は、東京都国際交流委員会が運営していたウェブサイトに掲載したものです。
8月のクローズアップでは、特定非営利活動法人 CWS Japanをご紹介します。世界30カ国以上で活動を行う国際NGOチャーチ・ワールド・サービス(CWS)の日本法人であるCWS Japanの活動は、2011年に起きた東日本大震災を契機としてスタートしました。未曽有の災害に見舞われた日本で、CWSの人道支援の経験を活かした様々な支援活動を展開し、現在はアジアの国々でも、自然災害、貧困、紛争などによって苦しい思いをしている人々の支援に取り組んでいます。今回は、CWS Japan事務局長の小美野剛さんに、これまでの活動の成果や今後の展望についてお話をうかがいました。
![]() CWSの歴史とCWS Japan設立の経緯を教えてください。
CWSの歴史とCWS Japan設立の経緯を教えてください。
 アメリカに本部を置くCWSは、第二次世界大戦後、*ララ物資と呼ばれる援助物資の提供を日本で行った団体の1つです。1946年にCWS日本委員会が東京に事務所を開設、1952年まで食糧・医療・医薬品などの配給活動を実施しました。その後は日本に事務所を構えての活動は行っていませんでしたが、2011年に発生した東日本大震災に対する緊急支援を行うために、CWSとして再び東京に事務所を開くことになったのです。地震・津波・原発事故が重なった複合災害への対応は先進国の日本といえども難しく、豊かな国だからこそ一人ひとりの生きる力が弱くなっているところもある。ゆえに先進国だから支援が必要ないというわけではなく、CWSの人道支援の経験が活きるはずだと考えたのです。当時バンコクにいた私が急きょ日本入りして事務所の開設を行い、東北三県の被災エリアの支援をスタートさせました。また、2013年にNPO法人CWS Japanの設立に至ってからは、アジアの国々でも支援活動を行うようになりました。東日本大震災の経験も含め、日本にあるリソースを海外で必要としているところに結び付ける橋渡しをすることも、私たちの重要な役割だと考えているのです。
アメリカに本部を置くCWSは、第二次世界大戦後、*ララ物資と呼ばれる援助物資の提供を日本で行った団体の1つです。1946年にCWS日本委員会が東京に事務所を開設、1952年まで食糧・医療・医薬品などの配給活動を実施しました。その後は日本に事務所を構えての活動は行っていませんでしたが、2011年に発生した東日本大震災に対する緊急支援を行うために、CWSとして再び東京に事務所を開くことになったのです。地震・津波・原発事故が重なった複合災害への対応は先進国の日本といえども難しく、豊かな国だからこそ一人ひとりの生きる力が弱くなっているところもある。ゆえに先進国だから支援が必要ないというわけではなく、CWSの人道支援の経験が活きるはずだと考えたのです。当時バンコクにいた私が急きょ日本入りして事務所の開設を行い、東北三県の被災エリアの支援をスタートさせました。また、2013年にNPO法人CWS Japanの設立に至ってからは、アジアの国々でも支援活動を行うようになりました。東日本大震災の経験も含め、日本にあるリソースを海外で必要としているところに結び付ける橋渡しをすることも、私たちの重要な役割だと考えているのです。
*敗戦直後の日本へ、アメリカから援助物資が贈られた。その活動Licensed Agencies for Relief in Asiaの頭文字をとってLARA(ララ)と呼ばれる。
![]() CWS Japanの活動には3つの柱があるそうですね。
CWS Japanの活動には3つの柱があるそうですね。
 「緊急・開発支援」、「政策提言」、「能力開発」、この3つが私たちの活動の柱です。 まず、緊急・開発支援ですが、国内では東日本大震災に続き、4月に起きた熊本地震の被災地でも緊急支援活動を行っています。また、海外の自然災害、貧困、紛争などの課題にも取り組んでおり、パキスタン北部の地震の被災者の越冬支援、ミャンマーの帰還民に対する給水設備の建設支援、アフガニスタンの女子教育の向上支援などを実施しています。 また、政策提言では、CWS Japanの強みである海外ネットワークを活かし、東日本大震災の支援などから得られた教訓や経験を世界に発信する活動を積極的に行っています。2015年3月に仙台で行われた第3回国連防災世界会議では、100団体以上が加盟する2015防災会議日本CSOネットワーク(JCC2015)の中心メンバーとして、同会議で採択される「仙台防災枠組」が日本の複合災害の教訓を反映したものとなるよう働きかけました。
「緊急・開発支援」、「政策提言」、「能力開発」、この3つが私たちの活動の柱です。 まず、緊急・開発支援ですが、国内では東日本大震災に続き、4月に起きた熊本地震の被災地でも緊急支援活動を行っています。また、海外の自然災害、貧困、紛争などの課題にも取り組んでおり、パキスタン北部の地震の被災者の越冬支援、ミャンマーの帰還民に対する給水設備の建設支援、アフガニスタンの女子教育の向上支援などを実施しています。 また、政策提言では、CWS Japanの強みである海外ネットワークを活かし、東日本大震災の支援などから得られた教訓や経験を世界に発信する活動を積極的に行っています。2015年3月に仙台で行われた第3回国連防災世界会議では、100団体以上が加盟する2015防災会議日本CSOネットワーク(JCC2015)の中心メンバーとして、同会議で採択される「仙台防災枠組」が日本の複合災害の教訓を反映したものとなるよう働きかけました。


熊本地震の緊急支援やアフガニスタンでの女子教育支援など、国内外で活動しています。
© CWS JAPAN
![]() 3つめの能力開発についてはいかがですか。
3つめの能力開発についてはいかがですか。
 能力開発では、支援に携わる人たちの知識と技術を向上させるために、人道支援の国際基準を日本で広めるための活動を行っています。NGOなどの複数団体が加盟する「支援の質とアカウンタビリティ向上ネットワーク(J-QAN)」の設立にも中心的に携わりました。これまで人道支援の国際基準を学ぶとなると海外からトレーナーを招く必要があったのですが、国際基準を教えられる日本人のトレーナーを育成し、日本人が日本語で教えるための教材も開発していきたいと考えています。
能力開発では、支援に携わる人たちの知識と技術を向上させるために、人道支援の国際基準を日本で広めるための活動を行っています。NGOなどの複数団体が加盟する「支援の質とアカウンタビリティ向上ネットワーク(J-QAN)」の設立にも中心的に携わりました。これまで人道支援の国際基準を学ぶとなると海外からトレーナーを招く必要があったのですが、国際基準を教えられる日本人のトレーナーを育成し、日本人が日本語で教えるための教材も開発していきたいと考えています。
なお、CWS Japanの3つの活動は、サイクルとして連動することが欠かせません。「緊急・開発支援」が傷口にバンドエイドを貼ることだとしたら、「政策提言」でそもそもケガをしないようにするためにはどうすればいいかを考え、同時に「能力開発」でより効率的で効果的なバンドエイドの貼り方を追究する、ということになります。3つの要素が揃うことで相乗効果が生まれ、初めてひとつの問題解決へとつながるのです。
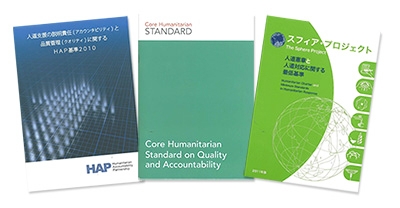
人道支援の国際基準の普及を目指す活動を積極的に行っています。
©CWS JAPAN
![]() CWS Japanは、国内外の様々なネットワークに参加されていますね。
CWS Japanは、国内外の様々なネットワークに参加されていますね。
 今、世界で起きている紛争・災害・格差などの問題は、ひとつの組織で解決できる規模をはるかに超えており、様々なセクターのリソースをつなげることでシナジーを生み出し、現状を打開するパワーを作っていくことが必要不可欠です。CWS Japanが共同事務局を務める防災・減災日本CSOネットワーク(JCC-DRR)とジャパンプラットフォーム(JPF)等の有志が中心となり、今年の3月にNGO、企業、政府がイノベーションによる人道支援の改革について議論する「Humanitarian Innovation Forum Japan 2016」を開催しました。現在はNGOと企業が協働してイノベーションを生み出していくプラットフォームの構築を目指して、いくつかのパイロットプロジェクトも動き出しています。こうして様々なセクターがひとつの問題解決をしていく仲間となるために大切なのは、やはり共感です。共感があって初めて共通のビジョンが生まれ、お互いが自分の強みを持ち寄ろうという動きになっていきます。様々なステークホルダーが連携しネットワークを作っていくノウハウを広めていくことも、CWS Japanの役割のひとつだと思っています。
今、世界で起きている紛争・災害・格差などの問題は、ひとつの組織で解決できる規模をはるかに超えており、様々なセクターのリソースをつなげることでシナジーを生み出し、現状を打開するパワーを作っていくことが必要不可欠です。CWS Japanが共同事務局を務める防災・減災日本CSOネットワーク(JCC-DRR)とジャパンプラットフォーム(JPF)等の有志が中心となり、今年の3月にNGO、企業、政府がイノベーションによる人道支援の改革について議論する「Humanitarian Innovation Forum Japan 2016」を開催しました。現在はNGOと企業が協働してイノベーションを生み出していくプラットフォームの構築を目指して、いくつかのパイロットプロジェクトも動き出しています。こうして様々なセクターがひとつの問題解決をしていく仲間となるために大切なのは、やはり共感です。共感があって初めて共通のビジョンが生まれ、お互いが自分の強みを持ち寄ろうという動きになっていきます。様々なステークホルダーが連携しネットワークを作っていくノウハウを広めていくことも、CWS Japanの役割のひとつだと思っています。


5月にトルコで行われた「世界人道サミット(WHS)」で発表する小美野事務局長。
WHSでは、国やセクターが連携して問題の解決にあたるという考えが採択された。
©CWS JAPAN
![]() ネットワークだからこそこんなことができた、という事例があれば教えてください。
ネットワークだからこそこんなことができた、という事例があれば教えてください。
 2015防災会議日本CSOネットワーク(JCC2015)の有志が集まり、福島の原発事故の教訓を海外に伝える『福島10の教訓』という冊子を作成、原発立地国の言語、14カ国語で発行しました。原発を持つか持たないかはその国の人たちが決めることです。しかしそれを決めるためのインフォームドコンセントが十分ではなく、リスクは隠される傾向にあります。それは「安全神話」を推進してきた日本が犯した過ちでもあり、福島の原発災害から学んだことを海外に伝えていく義務が日本人にはあるのではないか。そう考え、このような本を出したのです。本書の作成にあたっては、NGO関係者、研究者など多くの人たちにご協力いただきました。こうした仕事ができるのは、やはりネットワークの強みだと思いますね。
2015防災会議日本CSOネットワーク(JCC2015)の有志が集まり、福島の原発事故の教訓を海外に伝える『福島10の教訓』という冊子を作成、原発立地国の言語、14カ国語で発行しました。原発を持つか持たないかはその国の人たちが決めることです。しかしそれを決めるためのインフォームドコンセントが十分ではなく、リスクは隠される傾向にあります。それは「安全神話」を推進してきた日本が犯した過ちでもあり、福島の原発災害から学んだことを海外に伝えていく義務が日本人にはあるのではないか。そう考え、このような本を出したのです。本書の作成にあたっては、NGO関係者、研究者など多くの人たちにご協力いただきました。こうした仕事ができるのは、やはりネットワークの強みだと思いますね。
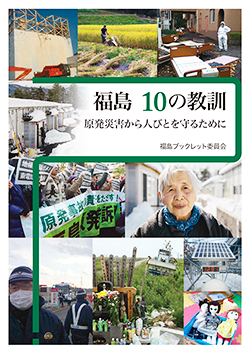
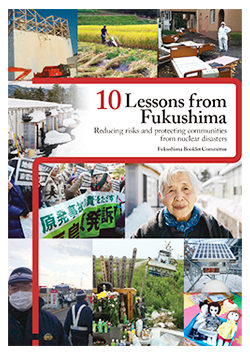
「福島10の教訓」は福島の教訓と声を伝えるために作られました。
©CWS JAPAN
![]() 日本をベースに活動を始められてから、どんなことを感じられましたか。
日本をベースに活動を始められてから、どんなことを感じられましたか。
 日本ではまだ、「NGOはボランティア」という考えが根強いですね。私は、NGOは人道支援と社会開発のプロであり、だからこそきちっとした報酬をもらうべきだとも考えています。そのために必要なのは、NGOが率先して自分たちはプロであるということを、実績を通して示し、周囲の意識を変えていくことです。単に貧しい地域に学校を建てましたというだけでなく、学校ができたことによって人々の生活や子どもの人生がどう変わったかというインパクトまで伝えきる。そして、それに共感した人が支援者になっていくという流れを作る必要があると思います。また、日本は様々な分野において縦割りの制度となっているため、そこにいかに「横串」を刺していくかというのも課題だと感じますね。
日本ではまだ、「NGOはボランティア」という考えが根強いですね。私は、NGOは人道支援と社会開発のプロであり、だからこそきちっとした報酬をもらうべきだとも考えています。そのために必要なのは、NGOが率先して自分たちはプロであるということを、実績を通して示し、周囲の意識を変えていくことです。単に貧しい地域に学校を建てましたというだけでなく、学校ができたことによって人々の生活や子どもの人生がどう変わったかというインパクトまで伝えきる。そして、それに共感した人が支援者になっていくという流れを作る必要があると思います。また、日本は様々な分野において縦割りの制度となっているため、そこにいかに「横串」を刺していくかというのも課題だと感じますね。
![]() CWS Japanの今後の展望をお聞かせください。
CWS Japanの今後の展望をお聞かせください。

 社会課題の分析は私たちNGOの強みですので、そこに企業や大学が持っているリソースをつなげて、新しい問題解決方法を生み出していきたいと考えています。そのためには私たちも積極的に新しいテクノロジーや研究などを学んでいかなければなりません。セクターを越え、企業や大学と連携することで、お互いの強みを活かした問題解決型のプロジェクトをどんどん増やしていきたいと思います。
社会課題の分析は私たちNGOの強みですので、そこに企業や大学が持っているリソースをつなげて、新しい問題解決方法を生み出していきたいと考えています。そのためには私たちも積極的に新しいテクノロジーや研究などを学んでいかなければなりません。セクターを越え、企業や大学と連携することで、お互いの強みを活かした問題解決型のプロジェクトをどんどん増やしていきたいと思います。
