クローズアップ
(認定)特定非営利活動法人 シェア=国際保健協力市民の会 ~誰もが安心して保健医療サービスを受けられる社会を目指して~

シェア=国際保健協力市民の会
在日外国人支援事業担当の山本裕子さん
*この記事は、東京都国際交流委員会が運営していたウェブサイトに掲載したものです。
11月のクローズアップでは、シェア=国際保健協力市民の会をご紹介します。シェアは、すべての人が心身ともに健康に暮らせる社会を目指し、“いのちを守る人を育てる”保健医療活動を、アジア、アフリカ、そして日本で進めている国際保健NGOです。シェアの願いは、誰もが基本的な保健医療サービスを受けられ、自分で自分の健康を改善していけるようになること。今回は、在日外国人を対象とした健康支援プロジェクトに焦点を当て、日本で暮らす外国人が抱える保健医療へのアクセスの問題と、その解決に向けシェアが行っている取組みについて、在日外国人支援事業担当の山本裕子さんにお話を伺いました。
![]() シェアが設立された経緯をお聞かせください。
シェアが設立された経緯をお聞かせください。
 シェアが誕生したのは1983年です。タイ・カンボジア国境でインドシナ難民の救援活動を行った医師・看護師・学生等が中心となって立ち上げました。現在は、タイ・カンボジア・東ティモールに海外拠点を構え、タイでエイズ対策、カンボジアで母子保健、東ティモールで学校保健に取り組んでいます。シェアの特徴は、主に保健分野で支援を行っていることです。実は、シェアも当初は医療支援を目指していたのですが、アフリカの緊急支援の現場で医師が直面したのは、同じ人が同じ病気で繰り返し病院にやって来るという現実でした。そこで、もっと根本から解決しよう、病気になる前に予防するところから始めようということで、私たちは保健支援に移行していったのです。また、シェアは日本国内でも、保健医療へのアクセスが困難な外国人を対象とした支援を行っています。
シェアが誕生したのは1983年です。タイ・カンボジア国境でインドシナ難民の救援活動を行った医師・看護師・学生等が中心となって立ち上げました。現在は、タイ・カンボジア・東ティモールに海外拠点を構え、タイでエイズ対策、カンボジアで母子保健、東ティモールで学校保健に取り組んでいます。シェアの特徴は、主に保健分野で支援を行っていることです。実は、シェアも当初は医療支援を目指していたのですが、アフリカの緊急支援の現場で医師が直面したのは、同じ人が同じ病気で繰り返し病院にやって来るという現実でした。そこで、もっと根本から解決しよう、病気になる前に予防するところから始めようということで、私たちは保健支援に移行していったのです。また、シェアは日本国内でも、保健医療へのアクセスが困難な外国人を対象とした支援を行っています。


![]() 医療機関にかかることが困難な在日外国人が少なくない原因はなんでしょうか。
医療機関にかかることが困難な在日外国人が少なくない原因はなんでしょうか。

電話相談に対応する山本さん。何度も電話や
メールのやり取りをするケースもあるそうです。
©SHARE
 やはり言葉の問題は大きいですね。たとえ日常会話ができても、細かく症状を説明したり、医師が伝える診断結果を理解するのは困難ですし、案内表記がすべて日本語であることも、病院へ行くハードルを上げる一因です。また、母国への仕送りなどでぎりぎりの生活をしている外国人の中には、医療費が心配で診療を受けに行くことができない方もいらっしゃいます。シェアではこのような在日外国人への支援として、無料出張健康相談会や医療電話相談を実施して、健康相談や医療機関の紹介を行ったり、言葉や医療制度といった問題に直面している外国人からの相談に対応しています。そして実は、シェアがより多くの相談を受けているのは、外国人を担当しているソーシャルワーカー、保健師、看護師、医師の方たちからなんです。外国人対応へのアドバイスや言葉の壁など、総合的な相談が多いですね。こうした直接外国人を支援する方たちに対して、公正な医療を提供してもらえるよう側方支援をすることが、私たちの活動の中心となっています。
やはり言葉の問題は大きいですね。たとえ日常会話ができても、細かく症状を説明したり、医師が伝える診断結果を理解するのは困難ですし、案内表記がすべて日本語であることも、病院へ行くハードルを上げる一因です。また、母国への仕送りなどでぎりぎりの生活をしている外国人の中には、医療費が心配で診療を受けに行くことができない方もいらっしゃいます。シェアではこのような在日外国人への支援として、無料出張健康相談会や医療電話相談を実施して、健康相談や医療機関の紹介を行ったり、言葉や医療制度といった問題に直面している外国人からの相談に対応しています。そして実は、シェアがより多くの相談を受けているのは、外国人を担当しているソーシャルワーカー、保健師、看護師、医師の方たちからなんです。外国人対応へのアドバイスや言葉の壁など、総合的な相談が多いですね。こうした直接外国人を支援する方たちに対して、公正な医療を提供してもらえるよう側方支援をすることが、私たちの活動の中心となっています。
![]() 医療現場において、言葉の壁を乗り越えるにはどうしたらいいのでしょうか。
医療現場において、言葉の壁を乗り越えるにはどうしたらいいのでしょうか。
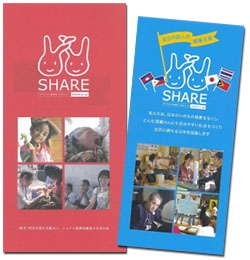
シェアの活動を紹介したリーフレットと
在日外国人の健康支援のリーフレット。
©SHARE
 医療関係者の多くは、病院に来る外国人が日本語を話せないのは自己責任だと思っており、手話や車椅子のように、ハンデを補う手段として通訳を提供するという考えにはなかなか至りません。そのため、患者側が通訳を準備できなければ診てもらえなかったり、診たとしても消極的な診療だけで帰されてしまったりすることもあります。また、病院側は「ボランティアでいいから通訳を連れて来て」と求めますが、実際に同行した家族や知人が頼まれるのは手術の説明やインフォームドコンセントなどの通訳で、とてもボランタリーでできるようなものではありません。子どもがシビアな告知の通訳をつとめ、心のケアが必要となるケースなどもみられます。これらの状況を改善するには、訓練された医療通訳を導入することは患者だけのメリットではないということを、医療機関に理解してもらう必要があると思います。
医療関係者の多くは、病院に来る外国人が日本語を話せないのは自己責任だと思っており、手話や車椅子のように、ハンデを補う手段として通訳を提供するという考えにはなかなか至りません。そのため、患者側が通訳を準備できなければ診てもらえなかったり、診たとしても消極的な診療だけで帰されてしまったりすることもあります。また、病院側は「ボランティアでいいから通訳を連れて来て」と求めますが、実際に同行した家族や知人が頼まれるのは手術の説明やインフォームドコンセントなどの通訳で、とてもボランタリーでできるようなものではありません。子どもがシビアな告知の通訳をつとめ、心のケアが必要となるケースなどもみられます。これらの状況を改善するには、訓練された医療通訳を導入することは患者だけのメリットではないということを、医療機関に理解してもらう必要があると思います。
![]() 医療通訳を導入すると、医療機関にはどのようなメリットがあるのでしょうか。
医療通訳を導入すると、医療機関にはどのようなメリットがあるのでしょうか。

シェアの医療従事者向けのセミナー。
医療通訳の必要性や活用方法などを伝えています。
©SHARE
 医療通訳の導入によって、医療機関は早期に診断を下し、病状や治療方針などの説明責任を果たすことができます。また、誤診を防いだり、患者と信頼関係を築いてスムーズに治療を行うことも可能になります。患者が連れて来るボランティア頼みではなく、病院側が医療通訳を用意する制度があった方が、通訳の費用がかかっても、結果的にコストパフォーマンスがよく、医療費の抑制にもつながるんです。アメリカ、カナダ、オーストラリアなどでは、言葉が通じないことによるさまざまな誤診やトラブルを経験したことから、国や自治体をあげて医療通訳派遣システムを整えています。日本でも、自治体と医療通訳派遣を専門にしているNPOが連携して、協定を結んだ病院に医療通訳を派遣する制度が一部の自治体で始まっていますが、通訳にコストがかかることは正当であるという理解がまだまだ進んでいないのが現状です。
医療通訳の導入によって、医療機関は早期に診断を下し、病状や治療方針などの説明責任を果たすことができます。また、誤診を防いだり、患者と信頼関係を築いてスムーズに治療を行うことも可能になります。患者が連れて来るボランティア頼みではなく、病院側が医療通訳を用意する制度があった方が、通訳の費用がかかっても、結果的にコストパフォーマンスがよく、医療費の抑制にもつながるんです。アメリカ、カナダ、オーストラリアなどでは、言葉が通じないことによるさまざまな誤診やトラブルを経験したことから、国や自治体をあげて医療通訳派遣システムを整えています。日本でも、自治体と医療通訳派遣を専門にしているNPOが連携して、協定を結んだ病院に医療通訳を派遣する制度が一部の自治体で始まっていますが、通訳にコストがかかることは正当であるという理解がまだまだ進んでいないのが現状です。
![]() シェアは医療通訳の育成・派遣は行っているのですか。
シェアは医療通訳の育成・派遣は行っているのですか。
 シェアでは、東京都の委託事業として結核に特化した通訳を育成し、都内で外国人の結核患者が出た場合に、保健師が病院や患者の自宅を訪問したり、保健所で患者の支援をする際の通訳派遣を行っています。この通訳派遣や相談事業を通して、医療通訳のメリットや導入の必要性を保健医療従事者に伝え、医療通訳の仕組みが必要だという声を現場から上げていけるようにすることも、私たちの役割のひとつです。
シェアでは、東京都の委託事業として結核に特化した通訳を育成し、都内で外国人の結核患者が出た場合に、保健師が病院や患者の自宅を訪問したり、保健所で患者の支援をする際の通訳派遣を行っています。この通訳派遣や相談事業を通して、医療通訳のメリットや導入の必要性を保健医療従事者に伝え、医療通訳の仕組みが必要だという声を現場から上げていけるようにすることも、私たちの役割のひとつです。
![]() 外国人の医療について現在気になっていることはありますか。
外国人の医療について現在気になっていることはありますか。
 日本でも、医療ツーリズムで訪日する外国人を対象とする医療通訳の整備を進めようとしていますが、日本に住んでいる外国人のための医療通訳の仕組みづくりの方が置きざりにされないか気になりますね。また、東京オリンピック開催に伴い外国人観光客が激増すると予想されますが、医療ツーリズムで来た人ではなく、一般の観光客が日本で病院にかかることになった場合、どうやって通訳を手配するのか、今のままでは医療機関が困るのは目に見えています。結局、訪日外国人・在日外国人というくくりにとらわれず、日本にいる外国人のための医療通訳の仕組みを整えていくことが重要だと思います。
日本でも、医療ツーリズムで訪日する外国人を対象とする医療通訳の整備を進めようとしていますが、日本に住んでいる外国人のための医療通訳の仕組みづくりの方が置きざりにされないか気になりますね。また、東京オリンピック開催に伴い外国人観光客が激増すると予想されますが、医療ツーリズムで来た人ではなく、一般の観光客が日本で病院にかかることになった場合、どうやって通訳を手配するのか、今のままでは医療機関が困るのは目に見えています。結局、訪日外国人・在日外国人というくくりにとらわれず、日本にいる外国人のための医療通訳の仕組みを整えていくことが重要だと思います。
![]() 今後、力を入れていきたい取組みがあればお聞かせください。
今後、力を入れていきたい取組みがあればお聞かせください。

 シェアはこれまで、結核、エイズと感染症の支援を行ってきましたが、在日外国人の母子保健や高齢化といった母数の大きい問題にも取り組んでいきたいです。地域で健康問題を解決していくようにするためには、自治体の保健センターや保健師の存在が外国人にとってもう少し身近なものになり、出産や介護について気軽に相談できる関係になることが必要だと思います。シェアは自治体やほかの団体と連携し、さらに外国人の方たちにも入ってもらって、一緒に問題を解決していくような取組みをしていきたいと考えています。日本人・外国人と区別するのではなく、同じ住民として、言葉のハンデがあるけれど補い合おうというふうになっていけたらいいですね。
シェアはこれまで、結核、エイズと感染症の支援を行ってきましたが、在日外国人の母子保健や高齢化といった母数の大きい問題にも取り組んでいきたいです。地域で健康問題を解決していくようにするためには、自治体の保健センターや保健師の存在が外国人にとってもう少し身近なものになり、出産や介護について気軽に相談できる関係になることが必要だと思います。シェアは自治体やほかの団体と連携し、さらに外国人の方たちにも入ってもらって、一緒に問題を解決していくような取組みをしていきたいと考えています。日本人・外国人と区別するのではなく、同じ住民として、言葉のハンデがあるけれど補い合おうというふうになっていけたらいいですね。
