クローズアップ
環境=文化NGO ナマケモノ倶楽部 ~本当の豊かさを求めて暮らしを見直す「スローライフのすすめ」~

ナマケモノ倶楽部 事務局長の馬場直子さん。
*この記事は、東京都国際交流委員会が運営していたウェブサイトに掲載したものです。
4月のクローズアップは、環境=文化NGO ナマケモノ倶楽部のご紹介です。いのちや人、自然とのつながりを大切にする「スローな社会」を目指して発足したこの市民団体は、「ナマケモノになろう!」を合言葉に、いのちの源である森を守る環境運動、できるだけエネルギーを使わないライフスタイルを提案する文化運動、フェアトレードや社会的起業を応援するスロービジネス運動の3つを柱として活動しています。今回は事務局長の馬場直子さんに、ナマケモノ倶楽部がスローライフを広めるために行っているさまざまな取組みについてお話を伺いました。
![]() ナマケモノ倶楽部が設立された経緯を教えてください。
ナマケモノ倶楽部が設立された経緯を教えてください。

©ナマケモノ倶楽部
 大学で文化人類学を教えている辻信一さん、環境活動家のアンニャ・ライトさん、フェアトレードコーヒーの輸入販売をしている中村隆市さんの3人が、生態系豊かな森が失われていくエクアドルを一緒に旅したことがきっかけで、1999年に発足しました。コンセプトはそれぞれの得意分野である文化、環境、エコビジネスを融合させた市民運動を作ることで、エクアドルにも生息しているナマケモノをシンボルとしました。動きがゆっくりでエネルギーをあまり使わないナマケモノは、とってもエコな生き物なんです。私たちはそんなナマケモノをお手本として、もっとスローダウンした暮らしをしようと提案しています。
大学で文化人類学を教えている辻信一さん、環境活動家のアンニャ・ライトさん、フェアトレードコーヒーの輸入販売をしている中村隆市さんの3人が、生態系豊かな森が失われていくエクアドルを一緒に旅したことがきっかけで、1999年に発足しました。コンセプトはそれぞれの得意分野である文化、環境、エコビジネスを融合させた市民運動を作ることで、エクアドルにも生息しているナマケモノをシンボルとしました。動きがゆっくりでエネルギーをあまり使わないナマケモノは、とってもエコな生き物なんです。私たちはそんなナマケモノをお手本として、もっとスローダウンした暮らしをしようと提案しています。
![]() ナマケモノ倶楽部が目指す「スローな社会」とはどのようなものなのでしょうか。
ナマケモノ倶楽部が目指す「スローな社会」とはどのようなものなのでしょうか。
 世界にはいろいろな環境問題がありますが、いくら「○○の森を守ろう」とか「絶滅が危惧される動物○○を守ろう」といった取組みをしても、今の社会のままでは根本的な解決には至りません。私たちは、日本を含む先進国の暮らしがさまざまな問題を引き起こしていることに目を向け、ライフスタイルの改善を市民レベルからやっていく必要があると考えました。そこで出てきたのがスローダウンという発想なんです。大量消費ではない暮らし方や大量生産ではない経済活動をどう作っていくか。経済効率が優先されていなかった時代の方が、生きていく上での豊かさは詰まっていたのではないか。そういったことを考え、暮らしを見直してみることを概して「スロー」と呼んでいるのです。
世界にはいろいろな環境問題がありますが、いくら「○○の森を守ろう」とか「絶滅が危惧される動物○○を守ろう」といった取組みをしても、今の社会のままでは根本的な解決には至りません。私たちは、日本を含む先進国の暮らしがさまざまな問題を引き起こしていることに目を向け、ライフスタイルの改善を市民レベルからやっていく必要があると考えました。そこで出てきたのがスローダウンという発想なんです。大量消費ではない暮らし方や大量生産ではない経済活動をどう作っていくか。経済効率が優先されていなかった時代の方が、生きていく上での豊かさは詰まっていたのではないか。そういったことを考え、暮らしを見直してみることを概して「スロー」と呼んでいるのです。
![]() 現在はどのような活動に力を入れていらっしゃいますか。
現在はどのような活動に力を入れていらっしゃいますか。
 ブータンの人たちの暮らしぶりを手がかりとして「本当の豊かさ」を問い直す、GNHキャンペーンです。GNHとはGross National Happiness=国民総幸福量のことで、ブータンの前国王が「大事なのはGNP(国民総生産)ではなくGNH、人々がどれだけ幸せを感じているかだ」と発言し、世界中から注目されました。ナマケモノ倶楽部では年2回、ブータンへのスタディツアーを行い、日本が失ってしまったような農村文化のコミュニティの絆や、お金やモノよりも大事なものがあるという価値観を学んでいます。
ブータンの人たちの暮らしぶりを手がかりとして「本当の豊かさ」を問い直す、GNHキャンペーンです。GNHとはGross National Happiness=国民総幸福量のことで、ブータンの前国王が「大事なのはGNP(国民総生産)ではなくGNH、人々がどれだけ幸せを感じているかだ」と発言し、世界中から注目されました。ナマケモノ倶楽部では年2回、ブータンへのスタディツアーを行い、日本が失ってしまったような農村文化のコミュニティの絆や、お金やモノよりも大事なものがあるという価値観を学んでいます。


本当の「豊かさ」を学ぶブータンのスタディツアー
©ナマケモノ倶楽部
![]() これまでの活動の中で、大きな手ごたえを感じたものを挙げていただけますか。
これまでの活動の中で、大きな手ごたえを感じたものを挙げていただけますか。
 まず、2003年に提唱した「100万人のキャンドルナイト」ですね。これは夏至の夜に2時間電気を消すことで、電気に依存しないことで得られる豊かさを見つけようというキャンペーンです。もともと私たちが「自主停電運動」という硬い名前(笑)で行っていたものを、ネーミングし直して全国規模でやろうと提案してくださった方々と実行委員会をつくり、一大ムーブメントとなりました。また、エクアドルの民話にヒントを得て2005年に立ち上げた「ハチドリのひとしずく」という温暖化防止キャンペーンも、じわじわと全国に広がりました。山火事を消すために小さなくちばしで水を運び続けたハチドリの物語そのものも、「小さくても自分にできることをしよう」という勇気を得られるお話として、さまざまな場面で使われるようになっています。
まず、2003年に提唱した「100万人のキャンドルナイト」ですね。これは夏至の夜に2時間電気を消すことで、電気に依存しないことで得られる豊かさを見つけようというキャンペーンです。もともと私たちが「自主停電運動」という硬い名前(笑)で行っていたものを、ネーミングし直して全国規模でやろうと提案してくださった方々と実行委員会をつくり、一大ムーブメントとなりました。また、エクアドルの民話にヒントを得て2005年に立ち上げた「ハチドリのひとしずく」という温暖化防止キャンペーンも、じわじわと全国に広がりました。山火事を消すために小さなくちばしで水を運び続けたハチドリの物語そのものも、「小さくても自分にできることをしよう」という勇気を得られるお話として、さまざまな場面で使われるようになっています。
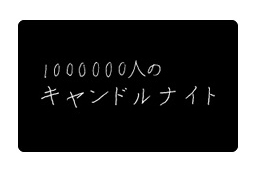
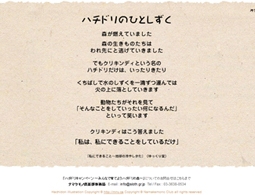
全国に広まった「100万人のキャンドルナイト」と「ハチドリのひとしずく」
©ナマケモノ倶楽部

アンペアダウンのWebサイトでは、
ご自宅の消費アンペアをチェックできます。
©ナマケモノ倶楽部
さらに、最近の活動だと「アンペアダウン」プロジェクトが挙げられます。これは家庭の電気のアンペア設定を見直して、必要以上に大きなアンペアで契約していた場合は1ランク下げようというもの。家庭のピーク電力を下げるアンペアダウンに多くの人が参加すれば、CO2排出量や発電量そのものを下げることにもつながります。東日本大震災の前からやっていたプロジェクトなのですが、震災後に多くの人がエネルギーに関心を持ち、メディアが取り上げてくれたことで一気に広まり実践する人が増えました。
![]() 活動を続ける中で、どんな課題があるとお考えですか。
活動を続ける中で、どんな課題があるとお考えですか。
 市民団体ゆえ、発信したことが浸透していくのに時間がかかることが多いので、長い目で取り組む必要があると考えています。また、いかに一人でも多くの人に関心を持つきっかけを提供できるかということも大きな課題ですね。できるだけかたい言葉や専門用語を使わずに、普通の人たちに「もっと知りたい」と思ってもらえるようなキャンペーンを作っていかなければと思っています。
市民団体ゆえ、発信したことが浸透していくのに時間がかかることが多いので、長い目で取り組む必要があると考えています。また、いかに一人でも多くの人に関心を持つきっかけを提供できるかということも大きな課題ですね。できるだけかたい言葉や専門用語を使わずに、普通の人たちに「もっと知りたい」と思ってもらえるようなキャンペーンを作っていかなければと思っています。
![]() スローライフをこれから実践する方たちへアドバイスをお願いします。
スローライフをこれから実践する方たちへアドバイスをお願いします。

「大切なのは、ちょっとずつでも
続けていくこと、楽しむこと」
と語る馬場さん。
 衣食住、いろいろな切り口があると思いますが、最初は食べ物から入るのがわかりやすいかもしれませんね。どんな生産者を応援するのか、どんな店で食べるのか、そういうことなら誰でも気負わずできるでしょう。休日にオーガニックやフェアトレードのものを提供しているカフェに行く、それも立派なスローライフです。大切なのは「細く長く」。小さなことでもいいから継続し、習慣にすることです。そして習慣にするためには、楽しむのが一番。ぜひ「スロー」を楽しく暮らしに取り入れてください。
衣食住、いろいろな切り口があると思いますが、最初は食べ物から入るのがわかりやすいかもしれませんね。どんな生産者を応援するのか、どんな店で食べるのか、そういうことなら誰でも気負わずできるでしょう。休日にオーガニックやフェアトレードのものを提供しているカフェに行く、それも立派なスローライフです。大切なのは「細く長く」。小さなことでもいいから継続し、習慣にすることです。そして習慣にするためには、楽しむのが一番。ぜひ「スロー」を楽しく暮らしに取り入れてください。
