クローズアップ
独立行政法人国際交流基金アジアセンター ~アジアと日本の架け橋となる人材を!“日本語パートナーズ”派遣事業~

国際交流基金アジアセンター主任、日本語事業チーム、
コミュニケーション企画チームの濱田祐生さん。
*この記事は、東京都国際交流委員会が運営していたウェブサイトに掲載したものです。
2月のクローズアップでは、独立行政法人国際交流基金アジアセンターが実施している“日本語パートナーズ”派遣事業をご紹介します。“日本語パートナーズ”とは、日本からASEAN諸国に派遣され、現地の日本語の先生やその生徒のパートナーとして活動する人たちのこと。日本語と日本文化の魅力を伝えるのはもちろん、現地の言語や文化・習慣を学び、双方向の交流を実現する役割を担います。2014年に始まったばかりの派遣事業について、アジアセンター主任の濱田祐生さんにお話を伺いました。
![]() 国際交流基金アジアセンターが設立された経緯について教えてください。
国際交流基金アジアセンターが設立された経緯について教えてください。

© 国際交流基金
 2013年12月に開催された日・ASEAN特別首脳会議において、日本政府は新しいアジア文化交流政策として「文化のWA(和・環・輪)プロジェクト~知り合うアジア~」を発表しました。東京オリンピック・パラリンピックが開催される2020年に向け、ASEANを中心とするアジア各国との文化交流事業を集中的に実施していくこのプロジェクトを担うため、2014年4月に国際交流基金の新たな部署として設立されたのがアジアセンターです。その使命はアジアの絆を強くすることであり、日本を含むアジア地域に住む人々が、交流や協働作業を通じてお互いのことをよく知り合い、アジアにともに生きる隣人としての共感や共生の意識を育んでいくことを目指して、「芸術・文化の双方向交流」と「日本語学習支援」の2つを柱として展開していきます。そして、柱のひとつである「日本語学習支援」を担うプロジェクトとしてスタートしたのが“日本語パートナーズ”派遣事業です。
2013年12月に開催された日・ASEAN特別首脳会議において、日本政府は新しいアジア文化交流政策として「文化のWA(和・環・輪)プロジェクト~知り合うアジア~」を発表しました。東京オリンピック・パラリンピックが開催される2020年に向け、ASEANを中心とするアジア各国との文化交流事業を集中的に実施していくこのプロジェクトを担うため、2014年4月に国際交流基金の新たな部署として設立されたのがアジアセンターです。その使命はアジアの絆を強くすることであり、日本を含むアジア地域に住む人々が、交流や協働作業を通じてお互いのことをよく知り合い、アジアにともに生きる隣人としての共感や共生の意識を育んでいくことを目指して、「芸術・文化の双方向交流」と「日本語学習支援」の2つを柱として展開していきます。そして、柱のひとつである「日本語学習支援」を担うプロジェクトとしてスタートしたのが“日本語パートナーズ”派遣事業です。
![]() “日本語パートナーズ”は何を目的として活動を行うのですか?
“日本語パートナーズ”は何を目的として活動を行うのですか?
 “日本語パートナーズ”は、ASEAN諸国にある主に中等教育機関、日本でいう高校に派遣されます。東南アジアにおける日本語学習者の数は113万人に上りますが、現地の日本語学習者は、日本に行ったことがない、または日本人と話す機会が少ないという人も多く、なかなか生の日本語を聞くことができないのが現状です。そこで、派遣先校に入った“日本語パートナーズ”は、日本語のネイティブ・スピーカーとして、現地の日本語の先生のサポートをすることと、日本語の学習をしている生徒たちに生の日本語に接してもらい、モチベーションを向上させることを目指して活動します。さらに、一方的に“教える”のではなく、現地の言葉や文化を学び、それを日本に持ち帰ってくることも“日本語パートナーズ”の活動目的のひとつです。
“日本語パートナーズ”は、ASEAN諸国にある主に中等教育機関、日本でいう高校に派遣されます。東南アジアにおける日本語学習者の数は113万人に上りますが、現地の日本語学習者は、日本に行ったことがない、または日本人と話す機会が少ないという人も多く、なかなか生の日本語を聞くことができないのが現状です。そこで、派遣先校に入った“日本語パートナーズ”は、日本語のネイティブ・スピーカーとして、現地の日本語の先生のサポートをすることと、日本語の学習をしている生徒たちに生の日本語に接してもらい、モチベーションを向上させることを目指して活動します。さらに、一方的に“教える”のではなく、現地の言葉や文化を学び、それを日本に持ち帰ってくることも“日本語パートナーズ”の活動目的のひとつです。
![]() “日本語パートナーズ”という名称がユニークですね。
“日本語パートナーズ”という名称がユニークですね。
 主役はあくまでも現地の日本語の先生であり、その良きパートナーとして、タイ人やインドネシア人の先生をサポートする。そこがこの事業の一番の特色です。日本語教育の現場にネイティブ・スピーカーが入ることで、生徒たちも楽しく勉強ができ、学習意欲が上がっていくことが期待されます。また、言葉だけでなく、さまざまな日本文化を派遣先校の生徒たちや地域の人たちに伝えてほしいと考えています。“日本語パートナーズ”派遣事業では、2020年までの7年間に3,000人以上を派遣する予定です。
主役はあくまでも現地の日本語の先生であり、その良きパートナーとして、タイ人やインドネシア人の先生をサポートする。そこがこの事業の一番の特色です。日本語教育の現場にネイティブ・スピーカーが入ることで、生徒たちも楽しく勉強ができ、学習意欲が上がっていくことが期待されます。また、言葉だけでなく、さまざまな日本文化を派遣先校の生徒たちや地域の人たちに伝えてほしいと考えています。“日本語パートナーズ”派遣事業では、2020年までの7年間に3,000人以上を派遣する予定です。
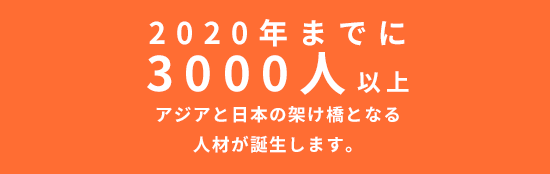
© 国際交流基金
![]() 応募者にはどういった方が多いのでしょうか?
応募者にはどういった方が多いのでしょうか?

2014年9月12日(金)に“日本語パートナーズ”
タイ1期29名が出発しました。
© 国際交流基金
 この事業は、応募可能な年齢が20歳から69歳までと門戸が広いのですが、中でも20代の学生と退職後のシニア世代からの応募が多く、両者で応募者の約6割を占めています。学生の場合は日本語教師になるための第一歩として考える方、シニア世代の場合はかつて東南アジアに滞在していた経験があり、そのときお世話になった恩返しをしたいという方などがいらっしゃいます。また、応募要件として日本語教育の資格や経験を求めているわけではないのですが、これまでの募集では、日本語教育を専攻している学生や日本語ボランティアの経験があるシニアの方から多数のご応募をいただいております。
この事業は、応募可能な年齢が20歳から69歳までと門戸が広いのですが、中でも20代の学生と退職後のシニア世代からの応募が多く、両者で応募者の約6割を占めています。学生の場合は日本語教師になるための第一歩として考える方、シニア世代の場合はかつて東南アジアに滞在していた経験があり、そのときお世話になった恩返しをしたいという方などがいらっしゃいます。また、応募要件として日本語教育の資格や経験を求めているわけではないのですが、これまでの募集では、日本語教育を専攻している学生や日本語ボランティアの経験があるシニアの方から多数のご応募をいただいております。
![]() 派遣中のパートナーからはどんな報告が寄せられていますか?
派遣中のパートナーからはどんな報告が寄せられていますか?
 一緒に過ごすうちに現地の先生の日本語の語彙がどんどん増えている、クラスでは恥ずかしがる生徒もいるが積極的に話そうという思いが伝わってくる、といった内容の報告が届いています。また、“日本語パートナーズ”が派遣された学校の先生たちからインドネシアの教育省経由で、学習者の意欲が高まっているというコメントが寄せられているとの連絡が届き、大変嬉しく思っています。
一緒に過ごすうちに現地の先生の日本語の語彙がどんどん増えている、クラスでは恥ずかしがる生徒もいるが積極的に話そうという思いが伝わってくる、といった内容の報告が届いています。また、“日本語パートナーズ”が派遣された学校の先生たちからインドネシアの教育省経由で、学習者の意欲が高まっているというコメントが寄せられているとの連絡が届き、大変嬉しく思っています。
![]() “日本語パートナーズ”は現地でどのような生活を送るのでしょうか?
“日本語パートナーズ”は現地でどのような生活を送るのでしょうか?
 住居は、国際交流基金アジアセンターがその国の標準的な家屋を手配します。トイレが現地式だったり、シャワーからお湯が出なかったりと戸惑うこともあるかと思いますが、工夫を重ねながら現地の生活に馴染んでいっていただきたいです。たとえば、インドネシアに派遣された“日本語パートナーズ”で、部屋に入ってくる虫への対処法を現地の先生に相談し、「部屋の周りにチョークで白線を引く」という方法を教えてもらった方がいらっしゃいます。現地で“日本語パートナーズ”をサポートする体制として、アジアセンターから現地の言葉や文化に通じた日本人調整員を派遣していますが、できる限り調整員に頼らずに、現地の人たちと交流しながら乗り越えていっていただけると嬉しいです。こうして海外で “外国人”として生活した経験を持つ人たちが増えていけば、日本で暮らす外国人が増えてきたときにもポジティブな効果が生まれるのではないかと期待しています。
住居は、国際交流基金アジアセンターがその国の標準的な家屋を手配します。トイレが現地式だったり、シャワーからお湯が出なかったりと戸惑うこともあるかと思いますが、工夫を重ねながら現地の生活に馴染んでいっていただきたいです。たとえば、インドネシアに派遣された“日本語パートナーズ”で、部屋に入ってくる虫への対処法を現地の先生に相談し、「部屋の周りにチョークで白線を引く」という方法を教えてもらった方がいらっしゃいます。現地で“日本語パートナーズ”をサポートする体制として、アジアセンターから現地の言葉や文化に通じた日本人調整員を派遣していますが、できる限り調整員に頼らずに、現地の人たちと交流しながら乗り越えていっていただけると嬉しいです。こうして海外で “外国人”として生活した経験を持つ人たちが増えていけば、日本で暮らす外国人が増えてきたときにもポジティブな効果が生まれるのではないかと期待しています。


左はタイ北部チェンライ県の授業中の生徒たち、右はインドネシア ジャカルタの教室風景。
© 国際交流基金
![]() 派遣前に行われる研修について教えてください。
派遣前に行われる研修について教えてください。

派遣前に1ヶ月間かけて行われる研修の様子
© 国際交流基金
 1ヶ月間の派遣前研修があり、現地の言語はもちろん、文化、風習、宗教や安全管理などの知識もしっかりと学んでいただきます。また、この研修を受ければ、日本語教育の経験がまったくない方でも、現地の先生と協力しながら“日本語パートナーズ”として活動する能力を身につけられるようになっていますし、日本の文化を伝えることに関してもいろいろなヒントが得られます。定番の折り紙や習字のほか、漫画やアニメ、キャラクター弁当や人気のデートスポットといった話題など、切り口はいくらでもあるのであまり難しく考えないでほしいですね。現地に入ってからも約1週間のオリエンテーションを設けており、実際に学校で活動を始める前に“日本語パートナーズ”として必要な最低限の能力を身につけていただくようになっています。
1ヶ月間の派遣前研修があり、現地の言語はもちろん、文化、風習、宗教や安全管理などの知識もしっかりと学んでいただきます。また、この研修を受ければ、日本語教育の経験がまったくない方でも、現地の先生と協力しながら“日本語パートナーズ”として活動する能力を身につけられるようになっていますし、日本の文化を伝えることに関してもいろいろなヒントが得られます。定番の折り紙や習字のほか、漫画やアニメ、キャラクター弁当や人気のデートスポットといった話題など、切り口はいくらでもあるのであまり難しく考えないでほしいですね。現地に入ってからも約1週間のオリエンテーションを設けており、実際に学校で活動を始める前に“日本語パートナーズ”として必要な最低限の能力を身につけていただくようになっています。
![]() 最後にメッセージをお願いします。
最後にメッセージをお願いします。

「この事業は2020年まで続きます。
ご自身のタイミングでご応募ください」
と語る濱田さん。
 多様なバックグラウンドを持った方たちに多様な日本文化を伝えていただくというのがこの事業のコンセプトであり、日本語教育の知識や経験がないからといって躊躇する必要はありません。この事業を通じて日本語や日本文化に興味を持つ人たちが増え、その人たちがいつか日本を訪れるというサイクルができることが我々の長期的な目標です。東南アジアでは、100万人以上の日本語学習者が日本語のネイティブ・スピーカーと接する機会を求めています。挑戦してみたいという気持ちのある方は、ぜひ応募をご検討ください。
多様なバックグラウンドを持った方たちに多様な日本文化を伝えていただくというのがこの事業のコンセプトであり、日本語教育の知識や経験がないからといって躊躇する必要はありません。この事業を通じて日本語や日本文化に興味を持つ人たちが増え、その人たちがいつか日本を訪れるというサイクルができることが我々の長期的な目標です。東南アジアでは、100万人以上の日本語学習者が日本語のネイティブ・スピーカーと接する機会を求めています。挑戦してみたいという気持ちのある方は、ぜひ応募をご検討ください。
●【アジアの絆を強くする。】"日本語パートナーズ"募集中!(動画)


